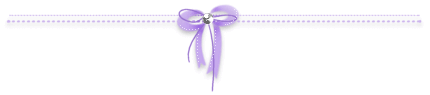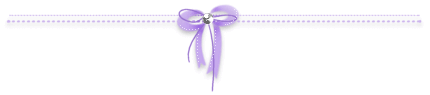
03

「てんくうとうぎじょう?」
少女達の大きな瞳が好奇心に輝く。その上目遣いに送られてくる視線に笑みで答えたヒソカは、唐突に行ってみないかと口にしたその場所についての説明を簡潔に行った。
「リングの上で相手と戦って、勝てば賞金が貰えるんだ」
「戦うの?」
「お小遣いもらえるの?」
「そう」
更に、勝ち進めばどんどん上の階に行き、逆に負ければ下がる。勝てば勝つほど相手は強くなり、賞金も法外な金額になるのだ。その金がどれほど価値のあるものなのか理解できない少女達は、しかしヒソカの言う強い相手とやらには興味があるようだった。
「行きたい!」
「戦いたい!」
ヒソカは常連だったが、少女達にとってはいわば、これはデビュー戦である。まだ何も知らない彼女達が、ゾルディック家で何を学んできたのか。それを知るべく、ヒソカはとの両名を連れて天空闘技場の扉を開いた。
「わくわくするね! 」
「ドキドキするね! 」
少女の甲高い声が、選手部屋に響いた。体格の良い男達の視線が、二人の少女へと突き刺さる。ガキが、こんな場所に何のようだ。全ての者が視線でそう訴える中、実際に口に出した男が居た。
「よう、お嬢ちゃんたち」
「?」
「悪いことは言わねェ。とっととお家へ帰んな」
それは帰る場所の無い二人にとっては、あまりに理解不能な言葉だった。
「どこに?」
「達、家なんてないよ」
本当にわからない、と首を傾げる少女に馬鹿にされていると思い込んだ男は、激昂する。口で言ってもわからないようなら、今ここでわからせてやると息巻く男だったが、もう暫くすれば出番がやってくるのである。ここはリングの上で戦う施設なのではなかっただろうか。否、確かにヒソカがそう言っていたのだ。
「でも、試合あるんでしょ?」
「このお部屋で戦っていいの?」
「そんなの関係ねェ! リングで恥かく前に、俺が教育しなおしてや――」
闘技場の外へと連れ出そうとでもしたのだろう。の襟首を掴もうと手を伸ばした男は、最後まで言葉を紡ぐことはできなかった。素早く男の手を弾いてその巨体を押したのはだったが、男がバランスを崩したのを見計らい、が足払いを食らわせたのである。ベンチや壁の道具たちを巻き込んで勢いよく倒れた男は、砂埃がおさまる頃にはすっかり目を回していた。
「……恥、かかなくて良かったね」
「教育なら、間に合ってるもんね」
自分達には今、しっかりと戦い方を教えてくれる師がいるのだ。他に教えを請う必要はない。
「とにはヒソカがいるから、教えてもらわなくて大丈夫なのに」
その名前を出した瞬間、選手達の間にどよめきの声が広がる。その凄まじいほどの困惑に、ヒソカとはそんなに名の通った人物なのかと思い呆然とは立ち尽くした。しかし、モニターを目にしたがあっと声を上げる。
「早く行こ、。もうはじまっちゃう」
自分達の番号は次だ。モニターで呼ばれるのを確認して、二人は会場へと足を運んだ。一階では数箇所のリングで一度に試合が行われる。その強さの度合いで、次に進む階が決まるのだろう。
「ねーなんでー?」
「なんでヒソカは一緒じゃないのー?」
両者、今し方素手で相手をぶちのめして来た齢十の少女は、可愛らしい声でヒソカを惑わせていた。凄まじい身体能力を見た審判は、二人を五十階へ行けと言っていたので、二人はその通りエレベーターで五十階へと上がったが、そこにヒソカの姿はなかった。案内された部屋に向かうと暫くしてヒソカがやって来たのだが、どうやら彼は二百階の住人らしく、そのことが少女達には不満だった。一緒に来たのに、と。
「僕は前からここを利用しているからね。五十階の相手なんて眠ってても倒せちゃうよ」
「……そっか、しょうがないなー」
「達もすぐにヒソカと同じところに行ける?」
「それはどうかな。君達が二百階に来る頃には、僕はもっと上にいるかも?」
人差し指を唇にあてるヒソカの茶目っ気たっぷりな物言いに、二人は唇を尖らせる。今の発言も、大変お気に召さなかったらしい。
「えー!? 戦い方教えてくれるって言ったのにー!」
「たくさん遊んでくれるって期待してたのにー!」
ブーイングの嵐に、ヒソカは首を竦めた。やれやれ、この少女達の相手は些か大変だ。イルミが投げ出したくなるのもわかるような気がするよと、それは心の中だけに留めておくことにして。
「試合がない時は遊びに来てあげるよ。そうだ、今から三人でトランプしようか」
「ほんと!?」
「やった、ヒソカ大好き!」
イルミはほとんど相手をしてくれなかったらしい。彼が相手にするのは、およそ暗殺の技術を学ぶときだけ。しかしそれも遊びの一環と捉えるこの少女達は、傍目から見てどれほど異端だろうか。恐らくは、幼少の頃のヒソカでさえも、ここまでの狂気はなかっただろう。ゾルディックの中でも特異なイルミですら、彼女達二人の秘める闇に驚いたほどなのだから。
とにかく二人は、自分達を連れ出したくせに唐突にヒソカに押し付けたイルミを恋しがったり恨んだりすることもなく、新たな保護者であるヒソカにすっかり懐いていた。彼の柔らかな口調と、真意がつかめない行動と、そこから生み出される奇術に、すっかり魅了されてしまったのだ。
「二百階についたら、新しい力を教えてあげるよ」
「聞いた? 」
「確かに、」
二人は顔を見合わせて頷くと、ヒソカの持つトランプを見つめてから指を差し、声を揃えた。
「そのまえに、しょうぶだー!」
「……はいはい」
とっても元気なコ達だ。これなら暫くは退屈しないで済みそうかな。
ヒソカは一層笑みを深くして、五十階に宛がわれた少女達の部屋に入っていった。
少女達の大きな瞳が好奇心に輝く。その上目遣いに送られてくる視線に笑みで答えたヒソカは、唐突に行ってみないかと口にしたその場所についての説明を簡潔に行った。
「リングの上で相手と戦って、勝てば賞金が貰えるんだ」
「戦うの?」
「お小遣いもらえるの?」
「そう」
更に、勝ち進めばどんどん上の階に行き、逆に負ければ下がる。勝てば勝つほど相手は強くなり、賞金も法外な金額になるのだ。その金がどれほど価値のあるものなのか理解できない少女達は、しかしヒソカの言う強い相手とやらには興味があるようだった。
「行きたい!」
「戦いたい!」
ヒソカは常連だったが、少女達にとってはいわば、これはデビュー戦である。まだ何も知らない彼女達が、ゾルディック家で何を学んできたのか。それを知るべく、ヒソカはとの両名を連れて天空闘技場の扉を開いた。
「わくわくするね! 」
「ドキドキするね! 」
少女の甲高い声が、選手部屋に響いた。体格の良い男達の視線が、二人の少女へと突き刺さる。ガキが、こんな場所に何のようだ。全ての者が視線でそう訴える中、実際に口に出した男が居た。
「よう、お嬢ちゃんたち」
「?」
「悪いことは言わねェ。とっととお家へ帰んな」
それは帰る場所の無い二人にとっては、あまりに理解不能な言葉だった。
「どこに?」
「達、家なんてないよ」
本当にわからない、と首を傾げる少女に馬鹿にされていると思い込んだ男は、激昂する。口で言ってもわからないようなら、今ここでわからせてやると息巻く男だったが、もう暫くすれば出番がやってくるのである。ここはリングの上で戦う施設なのではなかっただろうか。否、確かにヒソカがそう言っていたのだ。
「でも、試合あるんでしょ?」
「このお部屋で戦っていいの?」
「そんなの関係ねェ! リングで恥かく前に、俺が教育しなおしてや――」
闘技場の外へと連れ出そうとでもしたのだろう。の襟首を掴もうと手を伸ばした男は、最後まで言葉を紡ぐことはできなかった。素早く男の手を弾いてその巨体を押したのはだったが、男がバランスを崩したのを見計らい、が足払いを食らわせたのである。ベンチや壁の道具たちを巻き込んで勢いよく倒れた男は、砂埃がおさまる頃にはすっかり目を回していた。
「……恥、かかなくて良かったね」
「教育なら、間に合ってるもんね」
自分達には今、しっかりと戦い方を教えてくれる師がいるのだ。他に教えを請う必要はない。
「とにはヒソカがいるから、教えてもらわなくて大丈夫なのに」
その名前を出した瞬間、選手達の間にどよめきの声が広がる。その凄まじいほどの困惑に、ヒソカとはそんなに名の通った人物なのかと思い呆然とは立ち尽くした。しかし、モニターを目にしたがあっと声を上げる。
「早く行こ、。もうはじまっちゃう」
自分達の番号は次だ。モニターで呼ばれるのを確認して、二人は会場へと足を運んだ。一階では数箇所のリングで一度に試合が行われる。その強さの度合いで、次に進む階が決まるのだろう。
「ねーなんでー?」
「なんでヒソカは一緒じゃないのー?」
両者、今し方素手で相手をぶちのめして来た齢十の少女は、可愛らしい声でヒソカを惑わせていた。凄まじい身体能力を見た審判は、二人を五十階へ行けと言っていたので、二人はその通りエレベーターで五十階へと上がったが、そこにヒソカの姿はなかった。案内された部屋に向かうと暫くしてヒソカがやって来たのだが、どうやら彼は二百階の住人らしく、そのことが少女達には不満だった。一緒に来たのに、と。
「僕は前からここを利用しているからね。五十階の相手なんて眠ってても倒せちゃうよ」
「……そっか、しょうがないなー」
「達もすぐにヒソカと同じところに行ける?」
「それはどうかな。君達が二百階に来る頃には、僕はもっと上にいるかも?」
人差し指を唇にあてるヒソカの茶目っ気たっぷりな物言いに、二人は唇を尖らせる。今の発言も、大変お気に召さなかったらしい。
「えー!? 戦い方教えてくれるって言ったのにー!」
「たくさん遊んでくれるって期待してたのにー!」
ブーイングの嵐に、ヒソカは首を竦めた。やれやれ、この少女達の相手は些か大変だ。イルミが投げ出したくなるのもわかるような気がするよと、それは心の中だけに留めておくことにして。
「試合がない時は遊びに来てあげるよ。そうだ、今から三人でトランプしようか」
「ほんと!?」
「やった、ヒソカ大好き!」
イルミはほとんど相手をしてくれなかったらしい。彼が相手にするのは、およそ暗殺の技術を学ぶときだけ。しかしそれも遊びの一環と捉えるこの少女達は、傍目から見てどれほど異端だろうか。恐らくは、幼少の頃のヒソカでさえも、ここまでの狂気はなかっただろう。ゾルディックの中でも特異なイルミですら、彼女達二人の秘める闇に驚いたほどなのだから。
とにかく二人は、自分達を連れ出したくせに唐突にヒソカに押し付けたイルミを恋しがったり恨んだりすることもなく、新たな保護者であるヒソカにすっかり懐いていた。彼の柔らかな口調と、真意がつかめない行動と、そこから生み出される奇術に、すっかり魅了されてしまったのだ。
「二百階についたら、新しい力を教えてあげるよ」
「聞いた? 」
「確かに、」
二人は顔を見合わせて頷くと、ヒソカの持つトランプを見つめてから指を差し、声を揃えた。
「そのまえに、しょうぶだー!」
「……はいはい」
とっても元気なコ達だ。これなら暫くは退屈しないで済みそうかな。
ヒソカは一層笑みを深くして、五十階に宛がわれた少女達の部屋に入っていった。
to be continued...

- Back Top Next