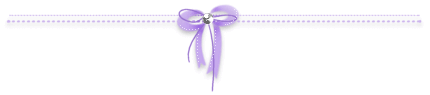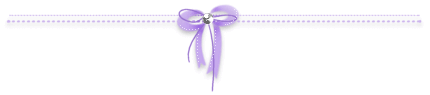
02

ゾルディック家の長男が幼女を屋敷に囲っているという噂を耳にしたヒソカは、その真偽を確かめるべくゾルディック家に乗り込んだ。殺しと家族以外には興味無さそうな顔をして、ヤることはしっかりヤっているんだなあ、と一人ごちたヒソカは、無用心にも開きっぱなしの扉を見つけ、無作法を承知でそこから侵入した。
「キミ達が、イルミのお人形かい?」
「だれ?」
「なに?」
二人、イルミの帰りを待っていた少女達は突然の来訪者に目を丸くする。窓から現れた不審者に対して恐怖や不安などは一切なく、ただ純粋な疑問だけを投げかけてくる。
「イルミはいないのかい?」
「出かけてるよ」
「お仕事行ってるよ」
「そうなんだ」
イルミがどのように彼女らを愛でているのか知りたかったヒソカだったが、逆にイルミがいないのならば都合が良いのかも知れない。この機に、どれ味見でもしてやろうかと手を伸ばした奇術師に、ストップの声がかかる。
「人の家に不法侵入しておいて、これ以上の狼藉を働くつもりか? ヒソカ」
「おや、イル――」
「イルミ、おかえり!」
「イルミ、あそんで!」
いつの間にやら帰宅して腕を組みドアに寄りかかっていたイルミへと、咎められても表情を変えないヒソカが声をかけるよりも先に、二人の少女が明るい顔で駆け寄った。何だかとても、懐かれているようである。いつものように冷たい眼差しを送るかと思いきや、イルミの両腕にぶら下がった少女達の頭を、彼は撫で付けたのである。イルミらしからぬ行動に、ヒソカはつい「キミ、本当にイルミ?」そう尋ねていた。
「ヒソカ、俺が偽者だって疑ってるの? 試してみる?」
「面白そうだけど、止めておくよ。ところで、随分とそのコ達を可愛がっているみたいだねェ」
それほどイイのかい? からかい半分に口にしたヒソカだったが、イルミは彼女達の頭を撫でる手を止めずにヒソカを見た。そして口を開く。
「いや、それがさ。前の仕事で拾ったんだ」
「拾った?」
「うん。本当は殺そうかとも思ったんだけど――」
ヒソカはあまり大きくないイルミの声に耳を傾ける。
――暗殺の素質があるんだ、この二人
「……へェ?」
その言葉に、ヒソカも大いに興味が沸いた。イルミは話を続けたが、それはそれは面白い。
仕事を終え、ターゲットである人買いの屋敷から少女達を連れ出したイルミは、弟達にするのと同じような暗殺訓練を少女達にさせた。一般人であるため最初は易しいものだったが、とという双子の娘は、それらをどんどん吸収した。火や雷などの耐久訓練はまだ行っていないものの、微量の毒であれば日常的に与えている。最初は不調を訴えることはあったが、今ではすっかり毒入りスープも毒リンゴも喜んで食べるようになっていた。
「でもさ、そろそろ面倒なんだよね」
「何がだい?」
「ヒソカが知ってるってことは、結構広まってるんだろ? この話」
僕が知っているのは君が幼女趣味に目覚めたって話だけど――なんてことは口に出さなかったヒソカだったが、その疑問を「そうに違いない」と決めて掛かっているイルミはこう続けた。
「こいつらのことを知ってるのは俺と俺の直属の執事が数人と、弟のミルキだけなんだよ」
「あれ、弟クンにも伝えてるんだ?」
「何かと、情報も欲しかったしね。ただミルキより下には伝えていない。カルトはまだ物心がついていないけど、最近キルアは同年代の子供に興味を示しているからさ」
暗殺者に友達は要らない。それはイルミや父親シルバが弟達に常々説いている教えであり、イルミ自身もそれを頑なに守り続けている。こうして対等に会話をしているヒソカとて仕事上のつながりでしかない。プライベートでも関わってくることは時折あるが、それはまず間違いなくヒソカ側の関与である。
「とにかく、ここのことがキルアにバレるのは避けたいんだ」
「ナルホド」
そして、イルミはヒソカにひとつの提案をする。
「だからさ、ヒソカ。二人を引き取らない?」
「……僕がかい?」
「うん。ヒソカ、好きだろ? こういう目をした子は」
ぽんぽん、と頭を叩かれたとは、イルミに向けていた視線を、今度はヒソカに向けてきた。その瞳は、やはりイルミが最初に彼女達を見たときと同じく深く闇を宿している。ヒソカですら、美しいと思ってしまうほどに。
「……そうだね。うん、気に入ったよ」
「じゃあ決まりだね」
「決まりなのかい? 随分と勝手だね」
「教育費必要なら言ってよ。この二人を連れてきたのは俺だしね」
気に入ったと言っただけなのに、有無を言わせず育ての親になれと言われたヒソカは、ところでイルミが彼女達に一切の気持ちの確認をしていないことが気になった。
「キミ達はそれでいいのかい? イルミが好きなんだろう?」
こんなにも懐いているというのに、家族にバレそうだからと他に押し付けるなんて、子供が犬猫を親で内緒で飼うようなものじゃないかとヒソカは思ったが、とに気にした様子は全くなかった。
「イルミが言うなら、どこに行ってもいいよ」
「遊んでくれるなら、誰だっていいよ!」
本当に、変わっている子供達だ。そう思うと同時に、ヒソカは俄然興味が沸いた。育てると言っても手のかかる赤ん坊ではないし、まだ義務教育と呼ばれる年齢の彼女達を、自分好みに育て上げて良い。暗にそう言われたヒソカは、ゾクゾクと昂ぶるのを感じた。
「それじゃ、二人は貰うよ。返せって言われてももう返さないよ? いいのかい?」
「うーん、たまに貸してくれればいいよ。ヒソカが立派な暗殺者に育ててくれれば俺はとても都合が良い」
「自分勝手だなァ。そんなキミも、嫌いじゃないけど」
恐らくゾルディック家で暗殺訓練を受けるのと、自己流で猟奇殺人鬼のヒソカが指導するのとでは全く意味が違う。次に二人がイルミに会うとき、果たしてそれは暗殺者として使い物になるのだろうか。ヒソカは二人を、暗殺者にする気はなかった。
「くっくっく……楽しみだねェ」
「どうしたの?」
「何が楽しいの?」
パドキア共和国から二人の少女を連れて出国したヒソカは、飛行船の中で楽しそうに笑った。少女達に問われても、ヒソカが答えることは無い。
実のところヒソカは、自分を殺せる程の使い手を、自分の手で育てられることに悦びを感じているのである。
「キミ達が、イルミのお人形かい?」
「だれ?」
「なに?」
二人、イルミの帰りを待っていた少女達は突然の来訪者に目を丸くする。窓から現れた不審者に対して恐怖や不安などは一切なく、ただ純粋な疑問だけを投げかけてくる。
「イルミはいないのかい?」
「出かけてるよ」
「お仕事行ってるよ」
「そうなんだ」
イルミがどのように彼女らを愛でているのか知りたかったヒソカだったが、逆にイルミがいないのならば都合が良いのかも知れない。この機に、どれ味見でもしてやろうかと手を伸ばした奇術師に、ストップの声がかかる。
「人の家に不法侵入しておいて、これ以上の狼藉を働くつもりか? ヒソカ」
「おや、イル――」
「イルミ、おかえり!」
「イルミ、あそんで!」
いつの間にやら帰宅して腕を組みドアに寄りかかっていたイルミへと、咎められても表情を変えないヒソカが声をかけるよりも先に、二人の少女が明るい顔で駆け寄った。何だかとても、懐かれているようである。いつものように冷たい眼差しを送るかと思いきや、イルミの両腕にぶら下がった少女達の頭を、彼は撫で付けたのである。イルミらしからぬ行動に、ヒソカはつい「キミ、本当にイルミ?」そう尋ねていた。
「ヒソカ、俺が偽者だって疑ってるの? 試してみる?」
「面白そうだけど、止めておくよ。ところで、随分とそのコ達を可愛がっているみたいだねェ」
それほどイイのかい? からかい半分に口にしたヒソカだったが、イルミは彼女達の頭を撫でる手を止めずにヒソカを見た。そして口を開く。
「いや、それがさ。前の仕事で拾ったんだ」
「拾った?」
「うん。本当は殺そうかとも思ったんだけど――」
ヒソカはあまり大きくないイルミの声に耳を傾ける。
――暗殺の素質があるんだ、この二人
「……へェ?」
その言葉に、ヒソカも大いに興味が沸いた。イルミは話を続けたが、それはそれは面白い。
仕事を終え、ターゲットである人買いの屋敷から少女達を連れ出したイルミは、弟達にするのと同じような暗殺訓練を少女達にさせた。一般人であるため最初は易しいものだったが、とという双子の娘は、それらをどんどん吸収した。火や雷などの耐久訓練はまだ行っていないものの、微量の毒であれば日常的に与えている。最初は不調を訴えることはあったが、今ではすっかり毒入りスープも毒リンゴも喜んで食べるようになっていた。
「でもさ、そろそろ面倒なんだよね」
「何がだい?」
「ヒソカが知ってるってことは、結構広まってるんだろ? この話」
僕が知っているのは君が幼女趣味に目覚めたって話だけど――なんてことは口に出さなかったヒソカだったが、その疑問を「そうに違いない」と決めて掛かっているイルミはこう続けた。
「こいつらのことを知ってるのは俺と俺の直属の執事が数人と、弟のミルキだけなんだよ」
「あれ、弟クンにも伝えてるんだ?」
「何かと、情報も欲しかったしね。ただミルキより下には伝えていない。カルトはまだ物心がついていないけど、最近キルアは同年代の子供に興味を示しているからさ」
暗殺者に友達は要らない。それはイルミや父親シルバが弟達に常々説いている教えであり、イルミ自身もそれを頑なに守り続けている。こうして対等に会話をしているヒソカとて仕事上のつながりでしかない。プライベートでも関わってくることは時折あるが、それはまず間違いなくヒソカ側の関与である。
「とにかく、ここのことがキルアにバレるのは避けたいんだ」
「ナルホド」
そして、イルミはヒソカにひとつの提案をする。
「だからさ、ヒソカ。二人を引き取らない?」
「……僕がかい?」
「うん。ヒソカ、好きだろ? こういう目をした子は」
ぽんぽん、と頭を叩かれたとは、イルミに向けていた視線を、今度はヒソカに向けてきた。その瞳は、やはりイルミが最初に彼女達を見たときと同じく深く闇を宿している。ヒソカですら、美しいと思ってしまうほどに。
「……そうだね。うん、気に入ったよ」
「じゃあ決まりだね」
「決まりなのかい? 随分と勝手だね」
「教育費必要なら言ってよ。この二人を連れてきたのは俺だしね」
気に入ったと言っただけなのに、有無を言わせず育ての親になれと言われたヒソカは、ところでイルミが彼女達に一切の気持ちの確認をしていないことが気になった。
「キミ達はそれでいいのかい? イルミが好きなんだろう?」
こんなにも懐いているというのに、家族にバレそうだからと他に押し付けるなんて、子供が犬猫を親で内緒で飼うようなものじゃないかとヒソカは思ったが、とに気にした様子は全くなかった。
「イルミが言うなら、どこに行ってもいいよ」
「遊んでくれるなら、誰だっていいよ!」
本当に、変わっている子供達だ。そう思うと同時に、ヒソカは俄然興味が沸いた。育てると言っても手のかかる赤ん坊ではないし、まだ義務教育と呼ばれる年齢の彼女達を、自分好みに育て上げて良い。暗にそう言われたヒソカは、ゾクゾクと昂ぶるのを感じた。
「それじゃ、二人は貰うよ。返せって言われてももう返さないよ? いいのかい?」
「うーん、たまに貸してくれればいいよ。ヒソカが立派な暗殺者に育ててくれれば俺はとても都合が良い」
「自分勝手だなァ。そんなキミも、嫌いじゃないけど」
恐らくゾルディック家で暗殺訓練を受けるのと、自己流で猟奇殺人鬼のヒソカが指導するのとでは全く意味が違う。次に二人がイルミに会うとき、果たしてそれは暗殺者として使い物になるのだろうか。ヒソカは二人を、暗殺者にする気はなかった。
「くっくっく……楽しみだねェ」
「どうしたの?」
「何が楽しいの?」
パドキア共和国から二人の少女を連れて出国したヒソカは、飛行船の中で楽しそうに笑った。少女達に問われても、ヒソカが答えることは無い。
実のところヒソカは、自分を殺せる程の使い手を、自分の手で育てられることに悦びを感じているのである。
to be continued...

- Back Top Next