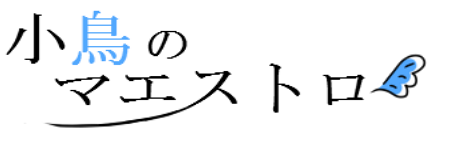

23

無理するな、と言われて仕事は全て取られてしまった。少しでも基礎体力、筋肉をつけるために鉛入りのベストだけは死守したけれど、男達は自分に体を鍛えては欲しくないようだ。
そもそもハンターとして女でも舐められないようにしなければならないし、試験官の女性や旅団員の女メンバーのように、念使いというのは心身ともに強くなければならないのだ。幻影旅団に軟禁されていたは、ここ数ヶ月で少しは逞しくなった気もするがまだ平均よりもずっと細い。筋力も昔より落ちてしまったように感じる。だからこそ、少しでも自身を鍛えなければならないのだ。
「薪割りくらいやらせてよ」
「こういうのは男の仕事だ!」
「ねぇゴン、私も一緒に」
「俺は一人でも大丈夫だよ!」
「クラピカ」
「……茶を、淹れてくれないか」
不満を顔に出せば、クラピカは視線を泳がせながらそう言った。この家は湯呑みであっても通常の何十倍もの重さがあるため、筋力アップにはなるはずだと、の内情を知っている彼なりの譲歩なのだろう。仕方なく、溜息まじりに台所へと立つ。するとそこへやってきた使用人のゼブロが背後で声を潜めて話しかけてきた。
「……貴女は念を使えるのでしょう。なら、特にここでの特訓は必要ないのではないですか?」
「……いえ。私は、彼らと対等でいたいから」
ゼブロはそうですかと呟いたのち、何でもなかったかのように出て行った。自分だけが一歩先にいるなんて思わない。むしろ、メンタル面では誰よりも未熟で、弱いのだと思う。逃げたくて逃げたくて仕方がない、強がってばかりの弱者だ。
「お茶入ったよ」
「わ、ありがとう!」
「悪ぃな」
「すまない」
薪割りに掃除に洗濯、それぞれの仕事を終えた三人のもとに湯呑みの乗ったお盆を運ぶ。約百キロ。重たくないはずもないが、ほんの少しだけ肉体強化して緩和する。顔色一つ変えずにお茶を運ぶを見て三人は驚いていたが、念を知らない彼らに教えてやることは禁忌である。ズシリと不穏な音を立ててテーブルに置かれた湯呑みを手に取り、一口啜ったレオリオが少し大袈裟に天井を仰いだ。
「いやー……二週間でかなり力がついた気がするぜ」
「そうだな、着実に目的に近づいてはいるだろう」
「もうすぐ、キルアに会えるんだね!」
そうやってゴンが嬉しそうに話すので、レオリオとクラピカは顔を見合わせて笑った。強大な力を持ちつつも根は楽観的な子どもだから、彼は周囲を安心させる。ゴンがいれば何とかなると思わせるのだ。もしかしたら自分も、旅団から逃げ延びることができるのでは……と、そこまで考えてはすぐに考えを撤回する。
ゴンがどれだけ強くても、旅団に敵うわけがない。淡い希望は、絶望にしかならないのだから。
「……キルアに会ったら、ゴンは何て言う?」
「え? うーん、久しぶり、かな」
何も変わらない。突然姿を消したことも、家族との確執も。彼はただキルアに会いたくて、それだけなのだ。
「久しぶり、か。いいね」
私が君たちの前から姿を消して、次に会った時にはヒトじゃなかったとしても、そう言ってくれる?
「……」
ふと浮かんだ言葉を飲み込んで、は微笑んだ。いいね、と。
「お世話になりました!」
パドキア共和国へ訪れてから一ヶ月が経過した。ビザの関係で今日中に出立しなくてはならない。それまでに、キルアに会わなくては。
一行はゼブロに礼を言い、小屋を後にした。
「……あれ?」
道なりに進むと、屋敷があるとゼブロは言っていた。しかし進んだ先に見えてきたのは、使用人の住む屋敷ではなく、一人の少女だった。
「出て行きなさい。ここから先は私有地よ」
燕尾服に身を纏い、杖を手にした褐色肌の少女は淡々と告げる。ふざけているのかわからない口上を述べながら、それでも瞳は鋭く隙を見せはしない。暗殺一家の使用人。見習いと言えど、その力は本物なのだ。
「この線から一歩でも出たら、実力で排除します」
「……」
「ゴン?」
怒りを孕んだ少年が一歩前へ足を踏み出した。少女は黙ってその行動を見ている。
「……ッ!!」
ゴンの左足が少女の引いた線を越えた瞬間、彼女は杖を大きく振りかぶり、ゴンの頬を殴りつける。軽い身体は宙を舞い、数メートル先まで吹き飛んだ。
友が攻撃を受けたことで即座に武器を手にした二人の仲間に、少年の待ったの声がかかる。
「レオリオクラピカ!! ……も、手を出しちゃダメだよ」
血をぬぐいながら立ち上がるゴン。手を出す以前に、レオリオとクラピカの両名とは違い自分は反応すらできなかったのだ。少女の攻撃が見えなかったわけじゃない。ただ、彼を守ろうだとか、仲間の敵だとか、そういう風には思えなかった。まだ、本当の意味で自分は彼らの仲間にはなっていないのかもしれない。そう思いながら、は懐のナイフを強く握った。こんなもの、持っていても何の役にも立たない。
「……ッ、ぐ」
ぽたりぽたりと血が滴る。痛々しく腫れ上がった頬と開かない目蓋。手を出すなと言われて微動だにせずその痛々しい姿を見守る三人に、堪らず少女が叫ぶ。
「もう、止めてよ……いい加減にしてッ! 無駄なの、わかるでしょ!!」
ゴンへ向けられていた視線をその後方へと向ける。
「あんたたちも止めてよ! 仲間なん……」
仲間なんでしょう、どうして止めないの。悲痛な声を飲み込まざるをえなかったのは、彼らの鋭い視線に怯んでしまったからだろう。にはなんとなく少女の気持ちが理解できた。
「なんで、かな……ただ、友達に会いに来ただけなのに。キルアに会いたいだけなのに、なんで、こんなことしなくちゃいけないんだッ!!」
ゴンの拳が石の柱を砕く。友達を試すのはおかしい、と主張を続ける彼はやはり純粋な気持ちでキルアのことを案じているのだ。
「君はミケとは違う。どんなに感情を隠そうとしたって、ちゃんと心がある。キルアの名前を出した時、一瞬だけど目が優しくなった」
そして、彼女も。
「お願い……キルア様を、助けてあげて」
パン。響いた銃声が、彼女のこめかみを穿った。
そもそもハンターとして女でも舐められないようにしなければならないし、試験官の女性や旅団員の女メンバーのように、念使いというのは心身ともに強くなければならないのだ。幻影旅団に軟禁されていたは、ここ数ヶ月で少しは逞しくなった気もするがまだ平均よりもずっと細い。筋力も昔より落ちてしまったように感じる。だからこそ、少しでも自身を鍛えなければならないのだ。
「薪割りくらいやらせてよ」
「こういうのは男の仕事だ!」
「ねぇゴン、私も一緒に」
「俺は一人でも大丈夫だよ!」
「クラピカ」
「……茶を、淹れてくれないか」
不満を顔に出せば、クラピカは視線を泳がせながらそう言った。この家は湯呑みであっても通常の何十倍もの重さがあるため、筋力アップにはなるはずだと、の内情を知っている彼なりの譲歩なのだろう。仕方なく、溜息まじりに台所へと立つ。するとそこへやってきた使用人のゼブロが背後で声を潜めて話しかけてきた。
「……貴女は念を使えるのでしょう。なら、特にここでの特訓は必要ないのではないですか?」
「……いえ。私は、彼らと対等でいたいから」
ゼブロはそうですかと呟いたのち、何でもなかったかのように出て行った。自分だけが一歩先にいるなんて思わない。むしろ、メンタル面では誰よりも未熟で、弱いのだと思う。逃げたくて逃げたくて仕方がない、強がってばかりの弱者だ。
「お茶入ったよ」
「わ、ありがとう!」
「悪ぃな」
「すまない」
薪割りに掃除に洗濯、それぞれの仕事を終えた三人のもとに湯呑みの乗ったお盆を運ぶ。約百キロ。重たくないはずもないが、ほんの少しだけ肉体強化して緩和する。顔色一つ変えずにお茶を運ぶを見て三人は驚いていたが、念を知らない彼らに教えてやることは禁忌である。ズシリと不穏な音を立ててテーブルに置かれた湯呑みを手に取り、一口啜ったレオリオが少し大袈裟に天井を仰いだ。
「いやー……二週間でかなり力がついた気がするぜ」
「そうだな、着実に目的に近づいてはいるだろう」
「もうすぐ、キルアに会えるんだね!」
そうやってゴンが嬉しそうに話すので、レオリオとクラピカは顔を見合わせて笑った。強大な力を持ちつつも根は楽観的な子どもだから、彼は周囲を安心させる。ゴンがいれば何とかなると思わせるのだ。もしかしたら自分も、旅団から逃げ延びることができるのでは……と、そこまで考えてはすぐに考えを撤回する。
ゴンがどれだけ強くても、旅団に敵うわけがない。淡い希望は、絶望にしかならないのだから。
「……キルアに会ったら、ゴンは何て言う?」
「え? うーん、久しぶり、かな」
何も変わらない。突然姿を消したことも、家族との確執も。彼はただキルアに会いたくて、それだけなのだ。
「久しぶり、か。いいね」
私が君たちの前から姿を消して、次に会った時にはヒトじゃなかったとしても、そう言ってくれる?
「……」
ふと浮かんだ言葉を飲み込んで、は微笑んだ。いいね、と。
「お世話になりました!」
パドキア共和国へ訪れてから一ヶ月が経過した。ビザの関係で今日中に出立しなくてはならない。それまでに、キルアに会わなくては。
一行はゼブロに礼を言い、小屋を後にした。
「……あれ?」
道なりに進むと、屋敷があるとゼブロは言っていた。しかし進んだ先に見えてきたのは、使用人の住む屋敷ではなく、一人の少女だった。
「出て行きなさい。ここから先は私有地よ」
燕尾服に身を纏い、杖を手にした褐色肌の少女は淡々と告げる。ふざけているのかわからない口上を述べながら、それでも瞳は鋭く隙を見せはしない。暗殺一家の使用人。見習いと言えど、その力は本物なのだ。
「この線から一歩でも出たら、実力で排除します」
「……」
「ゴン?」
怒りを孕んだ少年が一歩前へ足を踏み出した。少女は黙ってその行動を見ている。
「……ッ!!」
ゴンの左足が少女の引いた線を越えた瞬間、彼女は杖を大きく振りかぶり、ゴンの頬を殴りつける。軽い身体は宙を舞い、数メートル先まで吹き飛んだ。
友が攻撃を受けたことで即座に武器を手にした二人の仲間に、少年の待ったの声がかかる。
「レオリオクラピカ!! ……も、手を出しちゃダメだよ」
血をぬぐいながら立ち上がるゴン。手を出す以前に、レオリオとクラピカの両名とは違い自分は反応すらできなかったのだ。少女の攻撃が見えなかったわけじゃない。ただ、彼を守ろうだとか、仲間の敵だとか、そういう風には思えなかった。まだ、本当の意味で自分は彼らの仲間にはなっていないのかもしれない。そう思いながら、は懐のナイフを強く握った。こんなもの、持っていても何の役にも立たない。
「……ッ、ぐ」
ぽたりぽたりと血が滴る。痛々しく腫れ上がった頬と開かない目蓋。手を出すなと言われて微動だにせずその痛々しい姿を見守る三人に、堪らず少女が叫ぶ。
「もう、止めてよ……いい加減にしてッ! 無駄なの、わかるでしょ!!」
ゴンへ向けられていた視線をその後方へと向ける。
「あんたたちも止めてよ! 仲間なん……」
仲間なんでしょう、どうして止めないの。悲痛な声を飲み込まざるをえなかったのは、彼らの鋭い視線に怯んでしまったからだろう。にはなんとなく少女の気持ちが理解できた。
「なんで、かな……ただ、友達に会いに来ただけなのに。キルアに会いたいだけなのに、なんで、こんなことしなくちゃいけないんだッ!!」
ゴンの拳が石の柱を砕く。友達を試すのはおかしい、と主張を続ける彼はやはり純粋な気持ちでキルアのことを案じているのだ。
「君はミケとは違う。どんなに感情を隠そうとしたって、ちゃんと心がある。キルアの名前を出した時、一瞬だけど目が優しくなった」
そして、彼女も。
「お願い……キルア様を、助けてあげて」
パン。響いた銃声が、彼女のこめかみを穿った。
to be continued...

- Back Top Next
