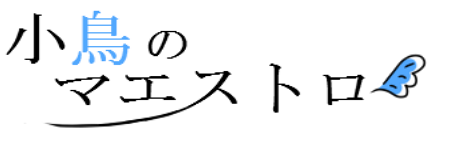

22

パドキア共和国は随分と賑わいを見せていた。暗殺一家が住んでいるとは思えないほど長閑な国のようだ。
「……観光バス?」
ゾルディック家について情報収集をしていたところ、どうやら彼の家は観光名所として有名らしい。イルミがあっさりとキルアの居場所を吐いたのはこのためか。
「これに乗って行くのが、近道だろうな……」
家族連れやカップルたちがカメラを手に続々とバスへ乗り込む中、一行は仕方なく列に続いた。ゴンだけは、周囲の観光客と変わらないテンションだったが。
「……」
バスに乗って気づいたのは、普通の観光客とは明らかに違う連中が混じっていること。
「……穏やかじゃないね」
「どうしたの、」
「ううん別に。何か見えた?」
もうすぐ友達に会える。そんな楽しそうなゴンの隣で、は外の景色を目に焼き付けていた。
「もうすぐだね」
もうすぐキルアに会える。そして、もうすぐこの旅も終わる。刻一刻と近づいてくる終わりのときに怯えながら、それでも最後まで彼らと共にありたいと願う。
「……?」
「なんでもないよ」
そう、迷う必要なんてない。これは自分で決めたことなのだから。
キルアと再会した後のことを考えれば気が重いが、それは会えなくても同じことだ。時間は有限。ならばせめて、悔いの残らないようにしたいと思う。
観光バスの車内でガイドの女性の声を聞きながら、はクラピカに薄い笑みを向けた。
「こちらが正門、別名黄泉への扉です」
聳え立つ鋼鉄の門、向こうには樹海が広がっており、ククルーマウンテンは遥か向こう。あまりのスケールの広さに、レオリオは持っていたトランクを地面に落とし「嘘だろ」と呟いた。
「ねぇガイドさん、中に入るにはどうしたらいいの?」
バスガイドの女性が生きては出られない等の説明を今し方していたのにもかかわらずそんなことを言ったゴンに流石だと脱帽する。
「坊や聞いてた? 中に入ったらもう生きては出られないのよ!?」
「ハッタリだろ」
男の言葉が女性の声を遮った。バスに乗ってきていた、明らかに観光客とは違う風貌。二人組の男は門の脇に設けられた小屋にいた守衛と思しき男性の胸倉を掴み上げ、所持していた鍵を奪った。しかし、そんな簡単に侵入できるものだろうか?
「あーあ、またミケがエサ以外の肉を食べちゃうよ」
「え……」
地に放られた男性がぼやいたのは暴力的な賊に対するものではなく、
「……!!!」
門の中から現れた、巨大な獣の腕のような何かに対しての言葉だった。ミケと呼ばれた、まるで犬猫のような名の得体の知れない猛獣。侵入者である二人の男の骸を放り捨て、中へと戻って行く。
「なに、あれ……」
おぞましい。身体中の毛が逆立つような感覚に見舞われて、戦慄する。
「バスを出せ! 早くここから離れるんだ!!」
一般観光客がざわめく。それもそうだろう、お伽話だとか誰も見たことのない伝説という現実味のないものだからこそ興味を持つのだ。目の前で人が死ねば誰だって恐ろしい。
「何してるんだあんたたちも早く乗れ!」
「あ、行っていいですよ。俺たちここに残ります」
「!?」
観光バスを見送って、守衛の男性に招かれるままに入った管理室で、ゴンは自分たちがハンター試験で知り合ったキルアの友人で、会いに来たのだということを伝えた。
「嬉しいねぇ。ここに勤めて二十年経つけど、友人として尋ねて来てくれたのはあんたたちが初めてだよ」
ゼブロと名乗ったその男は、ゾルディック一族を寂しい家だと言った。稀代の殺し屋一族なのだから当然と言えば当然だ。
「本当に嬉しいよ、ありがとう。……しかし、君らを庭内に入れるわけにはいかんです」
ゼブロが発した言葉に、嬉しそうだったゴンの表情が強張る。何故、と尋ねるよりも先に、彼はこう続けた。
「さっきのを見たでしょう? 無断で庭内に入ればミケに食い殺される」
「……」
穏やかな表情の奥に隠された思考が読めない。嬉しいと言った彼の言葉は本心ではあるのだろうが、それでも四人が屋敷へ行くのは反対のようだった。
「……守衛さん、あなたは何故無事なんですか?」
「!」
今まで黙って考え込んでいたクラピカが口を開いた。中に入るのならば鍵を持つ必要などない。相変わらずと言っていいほどの論理的名推理に感心していると、ゼブロが穏やかな声で「半分正解で半分はずれ」と言った。
「中には入るけど、鍵は使わない」
「え……?」
「あれは侵入者用の鍵でね」
本来の扉に鍵などかかっていない。それを聞いたレオリオは部屋を飛び出して門に手をかけたが、全くびくともしない。
「単純に力が足りないんですよ。この門さえ開けられないような輩は、ゾルディック家に入る資格なしということです」
住む世界が違うのだ、と思わずにはいられない。軽々とではないが、片側二トンという重さの扉を開けてしまう使用人。広大な土地。殺し屋一家という、肩書き。何も持っていない自分とはやはり格が違うのだと、思い知らされる。ただキルアには、同情と共感の余地があった。
全てを持って生まれてしまったからこそ、決められた運命を歩まなければならない現実。自らの意思で進むことを許されない事実。その一点において、はキルアに自分を重ねていた。全てを与えられて決定権を奪われたキルアと、全てを奪われて玩具としての生を決められた。
「もし良ければ、特訓しませんか。近くに私たち使用人の住む家があるんです」
彼は運命を憎んでいるだろうか。いつか、聞いてみたい。家族を捨ててまでハンター試験に臨んだこと、人生を終わらせるためにあの場所へ赴いた自分と同じように、
「ぜひ、お願いします」
運命に振り回されて生きるのは、もうたくさんだと。
「……観光バス?」
ゾルディック家について情報収集をしていたところ、どうやら彼の家は観光名所として有名らしい。イルミがあっさりとキルアの居場所を吐いたのはこのためか。
「これに乗って行くのが、近道だろうな……」
家族連れやカップルたちがカメラを手に続々とバスへ乗り込む中、一行は仕方なく列に続いた。ゴンだけは、周囲の観光客と変わらないテンションだったが。
「……」
バスに乗って気づいたのは、普通の観光客とは明らかに違う連中が混じっていること。
「……穏やかじゃないね」
「どうしたの、」
「ううん別に。何か見えた?」
もうすぐ友達に会える。そんな楽しそうなゴンの隣で、は外の景色を目に焼き付けていた。
「もうすぐだね」
もうすぐキルアに会える。そして、もうすぐこの旅も終わる。刻一刻と近づいてくる終わりのときに怯えながら、それでも最後まで彼らと共にありたいと願う。
「……?」
「なんでもないよ」
そう、迷う必要なんてない。これは自分で決めたことなのだから。
キルアと再会した後のことを考えれば気が重いが、それは会えなくても同じことだ。時間は有限。ならばせめて、悔いの残らないようにしたいと思う。
観光バスの車内でガイドの女性の声を聞きながら、はクラピカに薄い笑みを向けた。
「こちらが正門、別名黄泉への扉です」
聳え立つ鋼鉄の門、向こうには樹海が広がっており、ククルーマウンテンは遥か向こう。あまりのスケールの広さに、レオリオは持っていたトランクを地面に落とし「嘘だろ」と呟いた。
「ねぇガイドさん、中に入るにはどうしたらいいの?」
バスガイドの女性が生きては出られない等の説明を今し方していたのにもかかわらずそんなことを言ったゴンに流石だと脱帽する。
「坊や聞いてた? 中に入ったらもう生きては出られないのよ!?」
「ハッタリだろ」
男の言葉が女性の声を遮った。バスに乗ってきていた、明らかに観光客とは違う風貌。二人組の男は門の脇に設けられた小屋にいた守衛と思しき男性の胸倉を掴み上げ、所持していた鍵を奪った。しかし、そんな簡単に侵入できるものだろうか?
「あーあ、またミケがエサ以外の肉を食べちゃうよ」
「え……」
地に放られた男性がぼやいたのは暴力的な賊に対するものではなく、
「……!!!」
門の中から現れた、巨大な獣の腕のような何かに対しての言葉だった。ミケと呼ばれた、まるで犬猫のような名の得体の知れない猛獣。侵入者である二人の男の骸を放り捨て、中へと戻って行く。
「なに、あれ……」
おぞましい。身体中の毛が逆立つような感覚に見舞われて、戦慄する。
「バスを出せ! 早くここから離れるんだ!!」
一般観光客がざわめく。それもそうだろう、お伽話だとか誰も見たことのない伝説という現実味のないものだからこそ興味を持つのだ。目の前で人が死ねば誰だって恐ろしい。
「何してるんだあんたたちも早く乗れ!」
「あ、行っていいですよ。俺たちここに残ります」
「!?」
観光バスを見送って、守衛の男性に招かれるままに入った管理室で、ゴンは自分たちがハンター試験で知り合ったキルアの友人で、会いに来たのだということを伝えた。
「嬉しいねぇ。ここに勤めて二十年経つけど、友人として尋ねて来てくれたのはあんたたちが初めてだよ」
ゼブロと名乗ったその男は、ゾルディック一族を寂しい家だと言った。稀代の殺し屋一族なのだから当然と言えば当然だ。
「本当に嬉しいよ、ありがとう。……しかし、君らを庭内に入れるわけにはいかんです」
ゼブロが発した言葉に、嬉しそうだったゴンの表情が強張る。何故、と尋ねるよりも先に、彼はこう続けた。
「さっきのを見たでしょう? 無断で庭内に入ればミケに食い殺される」
「……」
穏やかな表情の奥に隠された思考が読めない。嬉しいと言った彼の言葉は本心ではあるのだろうが、それでも四人が屋敷へ行くのは反対のようだった。
「……守衛さん、あなたは何故無事なんですか?」
「!」
今まで黙って考え込んでいたクラピカが口を開いた。中に入るのならば鍵を持つ必要などない。相変わらずと言っていいほどの論理的名推理に感心していると、ゼブロが穏やかな声で「半分正解で半分はずれ」と言った。
「中には入るけど、鍵は使わない」
「え……?」
「あれは侵入者用の鍵でね」
本来の扉に鍵などかかっていない。それを聞いたレオリオは部屋を飛び出して門に手をかけたが、全くびくともしない。
「単純に力が足りないんですよ。この門さえ開けられないような輩は、ゾルディック家に入る資格なしということです」
住む世界が違うのだ、と思わずにはいられない。軽々とではないが、片側二トンという重さの扉を開けてしまう使用人。広大な土地。殺し屋一家という、肩書き。何も持っていない自分とはやはり格が違うのだと、思い知らされる。ただキルアには、同情と共感の余地があった。
全てを持って生まれてしまったからこそ、決められた運命を歩まなければならない現実。自らの意思で進むことを許されない事実。その一点において、はキルアに自分を重ねていた。全てを与えられて決定権を奪われたキルアと、全てを奪われて玩具としての生を決められた。
「もし良ければ、特訓しませんか。近くに私たち使用人の住む家があるんです」
彼は運命を憎んでいるだろうか。いつか、聞いてみたい。家族を捨ててまでハンター試験に臨んだこと、人生を終わらせるためにあの場所へ赴いた自分と同じように、
「ぜひ、お願いします」
運命に振り回されて生きるのは、もうたくさんだと。
to be continued...

- Back Top Next
