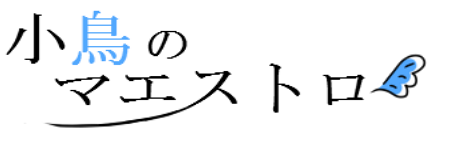

20

パドキア共和国へ向かう飛行船の中だった。キルアの兄イルミから実家の所在地を聞いた四人は試験会場のパソコンからその場所を調べた。飛行船を予約して、すぐにそれに乗り込んだのだ。
キルアに会えるという喜びから、既にイルミに対する怒りなど忘れて飛行船ではしゃぐゴンとそれに呆れつつも年長として保護者がわりで付き合ってやるレオリオだったが、賑やかな彼らとは対照的に、クラピカとの口数はとても少ない。
「……」
しかしレオリオがその理由を聞かないでいるのは、クラピカがヒソカと言葉を交わしたのを目にしていたし、に至ってはただキルアの安否を心配しているのだろうという結論に達した。考えてみればそれは当然で、目の前のゴン少年のようにただ友達の家に行くんだからと楽しそうにしている方が不自然なのだ。
「あ、ねぇ見てよレオリオ! あれ何かな?」
「ったくよぉ」
特に気にしないようにして、レオリオははしゃぐゴンをたしなめつつもそちらへと向かう。
二人が離れた場で、クラピカは細く長く息を吐く。
「」
不意に名前を呼ばれてびくりと肩が震えた。クラピカは自分自身が彼女に何か無礼を働いた記憶はなく、その様子に目を細めた。
「……どうかしたか」
「いや、えっと……何もないけど」
「……」
「クラピカこそ何か用があった?」
それは、何気なく口をついて出た言葉だった。自分の不安を悟られぬよう、つとめて平静を装って、ようやく告げた言葉だった。のだが、
「……ヒソカと、話をしたんだ」
「!」
「最終試験でな……講習の時に聞いただろう。不本意では、あったが」
クラピカとヒソカの試合に引っ掛かりを覚えたポックルがあの場で不満を口にしていなければ、はヒソカがクラピカに接触していたことを知らないままだっただろう。あの時にはヒソカはただ意味深な笑みを浮かべるだけで話す気はないようであったので、あえて気にしないようにしていた。それは到底無理な話なのだが。
「うん」
搾り出した声は、何てことない相槌。は視線を地面に落としたまま、自分の膝に顔をうずめた。次の言葉を聞きたくなかった。けれど、耳を塞ぐことはできなかった。
「全部、聞いた」
「……」
「お前と蜘蛛の……幻影旅団の因縁についてだ」
「そう」
ヒソカの口は空気のように軽い。だから特別驚くこともないけれど、しかしクラピカが冷静なことのほうが気にかかる。
「……驚いていないの?」
「無論驚いている。が、が何かを隠しているのはわかっていたからな。合点がいった、というのが正しい」
「そういうものなのかな……」
クラピカは気まずそうにに視線をやる。しかしは、一向にクラピカのほうを見ようとしない。見れるわけがなかった。
「黙っててごめんね。クラピカが復讐のことを話してくれたときに、私は秘密にしようって思ったんだ」
「私を愚かなやつだと思ったか」
その質問に、ようやくは顔を上げた。揺れる瞳でクラピカを見て、小さく唇を動かした。
「正直、わからない。でも、そうだね、少し思ったよ。ううん、今でも無謀だって思ってる」
ずっと囚われの身だったのだ。これからもきっとそうなる。はこれからもずっと、奴等の影に怯え続けなければならないのだ。
「私は幻影旅団団長の所有物。愛玩。奴隷。こんな声持っていたって、全然綺麗じゃないの。おかしいよね」
いっそ喉を潰してしまえばと、何度思ったことか。けれど、どれだけ皮膚を裂こうがクロロに逆らおうが、それだけはできなかった。
「声が無くなれば、解放されるって思ったけど……それってつまり私に存在価値がなくなるんだから、彼らが私を生かす理由もないんだよね」
生きていたとしても、歌えないのでは自分は死んだも同然。声を失えば、その瞬間に一族としての自分は死ぬ。念もほとんどが使えなくなるので、生き残る術が無くなるのだ。
「だから私は、死ぬためにハンター試験を受けた」
クラピカは一瞬だけ、目を見開いて小さく「だからか」と呟く。彼はここでようやく、が試験に消極的なわけを理解し、納得したのだった。
「だから、君は――旅団の奴らが自分を捕らえに来るのを恐れているのか」
「……」
こくり。静かに頭を落としたは、小さな子供のように蹲っていた。
「死にたくないって、思ったから……ゴンやキルア、レオリオ、それからクラピカ。みんなに会えたから、私、生きたくなったの」
出来るところまで、みっともなく足掻いてみようと思った。
「今、旅団の誰かが目の前に現われたら、きっと私は自分の意思で檻の中に戻る」
植えつけられた記憶は頭の奥で囁く。お前は逃げられやしないのだと。しかしそれならいっそ、今だけはこのままでいたい。自分から初めて関わりたいと思った彼らの、自分を初めて友人と認めてくれた彼らの、仲間でいたいのだ。
「ゴンたちには、言わないでね」
弱々しく吐き出されたの本音に、クラピカもまた小さく頷いた。
言えるはずもない。他人が口にするには、彼女の背負うものはあまりに重すぎる。
「……もし、」
会話を打ち切ろうとしていたを止めるように、暫く黙っていたクラピカが口を開いた。それは、仮定の話。
「もしも私が、蜘蛛を倒し復讐を終えたなら――君はどうするんだ」
仮定であって、仮定ではない。クラピカの目には、必ずそうするという強い意思が見える。
「できるわけ」
ない。言葉を飲み込んで、はクラピカの「もしも」話に乗っかることにした。
「……もし、旅団が滅びたら。私は自由になれる。そうすれば故郷に帰れるし、私は」
本当にずっと望んでいたこと。囚われの身となってからは感じたことのないそれ。
「自由に、歌える」
元来は空を統べる鳥の一族が、羽を毟られ地べたに引き摺り下ろされた。それでもやつらは嘲いのたまうのだ。歌え、と。
「でもそんなことできるわけないから、私は信じない。応援なんかしない。絶対に」
本当は止めて欲しい。彼らには誰も敵うはずが無いのだ。けれどそれが無理な頼みであることも重々承知しているので、
「私はこの件に関して、君に干渉したりはしない。旅団が死のうがクラピカが死のうが、どちらの結果になっても私にそれを止める権利はない」
「……そうか」
本当は勝って欲しい。旅団を滅ぼして、自分を救って欲しい。けれどそんなこと言えるはずもない。自分の存在は重荷にしかならない。結果として辛辣な言葉が羅列したが、それを全て聞いたクラピカの口元には笑みが浮かぶ。
「ならば私も、自由にやるとしよう」
「!」
お前はそれでいいのだと、言ってもらえた気がした。
飛行船はパドキア共和国を目指して飛び続ける。どうかこの旅がまだ、終わりませんように。
キルアに会えるという喜びから、既にイルミに対する怒りなど忘れて飛行船ではしゃぐゴンとそれに呆れつつも年長として保護者がわりで付き合ってやるレオリオだったが、賑やかな彼らとは対照的に、クラピカとの口数はとても少ない。
「……」
しかしレオリオがその理由を聞かないでいるのは、クラピカがヒソカと言葉を交わしたのを目にしていたし、に至ってはただキルアの安否を心配しているのだろうという結論に達した。考えてみればそれは当然で、目の前のゴン少年のようにただ友達の家に行くんだからと楽しそうにしている方が不自然なのだ。
「あ、ねぇ見てよレオリオ! あれ何かな?」
「ったくよぉ」
特に気にしないようにして、レオリオははしゃぐゴンをたしなめつつもそちらへと向かう。
二人が離れた場で、クラピカは細く長く息を吐く。
「」
不意に名前を呼ばれてびくりと肩が震えた。クラピカは自分自身が彼女に何か無礼を働いた記憶はなく、その様子に目を細めた。
「……どうかしたか」
「いや、えっと……何もないけど」
「……」
「クラピカこそ何か用があった?」
それは、何気なく口をついて出た言葉だった。自分の不安を悟られぬよう、つとめて平静を装って、ようやく告げた言葉だった。のだが、
「……ヒソカと、話をしたんだ」
「!」
「最終試験でな……講習の時に聞いただろう。不本意では、あったが」
クラピカとヒソカの試合に引っ掛かりを覚えたポックルがあの場で不満を口にしていなければ、はヒソカがクラピカに接触していたことを知らないままだっただろう。あの時にはヒソカはただ意味深な笑みを浮かべるだけで話す気はないようであったので、あえて気にしないようにしていた。それは到底無理な話なのだが。
「うん」
搾り出した声は、何てことない相槌。は視線を地面に落としたまま、自分の膝に顔をうずめた。次の言葉を聞きたくなかった。けれど、耳を塞ぐことはできなかった。
「全部、聞いた」
「……」
「お前と蜘蛛の……幻影旅団の因縁についてだ」
「そう」
ヒソカの口は空気のように軽い。だから特別驚くこともないけれど、しかしクラピカが冷静なことのほうが気にかかる。
「……驚いていないの?」
「無論驚いている。が、が何かを隠しているのはわかっていたからな。合点がいった、というのが正しい」
「そういうものなのかな……」
クラピカは気まずそうにに視線をやる。しかしは、一向にクラピカのほうを見ようとしない。見れるわけがなかった。
「黙っててごめんね。クラピカが復讐のことを話してくれたときに、私は秘密にしようって思ったんだ」
「私を愚かなやつだと思ったか」
その質問に、ようやくは顔を上げた。揺れる瞳でクラピカを見て、小さく唇を動かした。
「正直、わからない。でも、そうだね、少し思ったよ。ううん、今でも無謀だって思ってる」
ずっと囚われの身だったのだ。これからもきっとそうなる。はこれからもずっと、奴等の影に怯え続けなければならないのだ。
「私は幻影旅団団長の所有物。愛玩。奴隷。こんな声持っていたって、全然綺麗じゃないの。おかしいよね」
いっそ喉を潰してしまえばと、何度思ったことか。けれど、どれだけ皮膚を裂こうがクロロに逆らおうが、それだけはできなかった。
「声が無くなれば、解放されるって思ったけど……それってつまり私に存在価値がなくなるんだから、彼らが私を生かす理由もないんだよね」
生きていたとしても、歌えないのでは自分は死んだも同然。声を失えば、その瞬間に一族としての自分は死ぬ。念もほとんどが使えなくなるので、生き残る術が無くなるのだ。
「だから私は、死ぬためにハンター試験を受けた」
クラピカは一瞬だけ、目を見開いて小さく「だからか」と呟く。彼はここでようやく、が試験に消極的なわけを理解し、納得したのだった。
「だから、君は――旅団の奴らが自分を捕らえに来るのを恐れているのか」
「……」
こくり。静かに頭を落としたは、小さな子供のように蹲っていた。
「死にたくないって、思ったから……ゴンやキルア、レオリオ、それからクラピカ。みんなに会えたから、私、生きたくなったの」
出来るところまで、みっともなく足掻いてみようと思った。
「今、旅団の誰かが目の前に現われたら、きっと私は自分の意思で檻の中に戻る」
植えつけられた記憶は頭の奥で囁く。お前は逃げられやしないのだと。しかしそれならいっそ、今だけはこのままでいたい。自分から初めて関わりたいと思った彼らの、自分を初めて友人と認めてくれた彼らの、仲間でいたいのだ。
「ゴンたちには、言わないでね」
弱々しく吐き出されたの本音に、クラピカもまた小さく頷いた。
言えるはずもない。他人が口にするには、彼女の背負うものはあまりに重すぎる。
「……もし、」
会話を打ち切ろうとしていたを止めるように、暫く黙っていたクラピカが口を開いた。それは、仮定の話。
「もしも私が、蜘蛛を倒し復讐を終えたなら――君はどうするんだ」
仮定であって、仮定ではない。クラピカの目には、必ずそうするという強い意思が見える。
「できるわけ」
ない。言葉を飲み込んで、はクラピカの「もしも」話に乗っかることにした。
「……もし、旅団が滅びたら。私は自由になれる。そうすれば故郷に帰れるし、私は」
本当にずっと望んでいたこと。囚われの身となってからは感じたことのないそれ。
「自由に、歌える」
元来は空を統べる鳥の一族が、羽を毟られ地べたに引き摺り下ろされた。それでもやつらは嘲いのたまうのだ。歌え、と。
「でもそんなことできるわけないから、私は信じない。応援なんかしない。絶対に」
本当は止めて欲しい。彼らには誰も敵うはずが無いのだ。けれどそれが無理な頼みであることも重々承知しているので、
「私はこの件に関して、君に干渉したりはしない。旅団が死のうがクラピカが死のうが、どちらの結果になっても私にそれを止める権利はない」
「……そうか」
本当は勝って欲しい。旅団を滅ぼして、自分を救って欲しい。けれどそんなこと言えるはずもない。自分の存在は重荷にしかならない。結果として辛辣な言葉が羅列したが、それを全て聞いたクラピカの口元には笑みが浮かぶ。
「ならば私も、自由にやるとしよう」
「!」
お前はそれでいいのだと、言ってもらえた気がした。
飛行船はパドキア共和国を目指して飛び続ける。どうかこの旅がまだ、終わりませんように。
to be continued...

- Back Top Next
