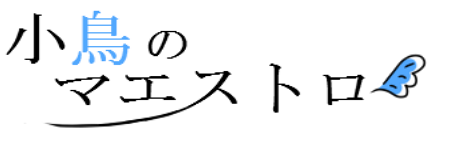

13

歌を歌うことは、その一族にとっては極普通の、当たり前のことだった。
過去には海辺で暮らしていたこともあったらしいけれど、魔力のこもった歌声は船乗り達から忌み嫌われ、逃げるようにして森の奥深くに小さな集落を作り暮らすことを選んだ。当時の子供達は、誰に邪魔されることもなく、自由に歌を歌えた。私もその中の一人で、よく集落を抜け出して森の奥で歌っていた。観客は森と、そこに住む小動物たちだけ。あの男に会うまでは。
私は親の顔を知らない。父は外の男で、母は私を生んで間も無く死んだ。男に捨てられて自ら命を絶った愚かな女だと、一族の恥さらしと言われていた。よく知らないその人のことを、私は他人事のように聞いた。馬鹿な人だと。自分は、そんな風にはなりたくないと。
自害とは、最も愚かで罪深い行為だ。幼心に、強い女になりたいと強く思うようになったのだった。男に頼らずとも、私は生きていける。そう思った。
私の育ての親で一族の長老でもある婆様は、私が適齢期である十二になると念の存在を伝えた。歌を、オーラに込めて歌う方法を教えた。無差別に外の人間を襲っていた力を、制御する方法と、自由に歌うための力を学ばせてくれた。それでも外の世界は危険だからと子供達は森の外へ行くことは禁じられ、私はただひたすらに歌に願いを込めて歌った。そして、あの日も。
女系一族であるセルミアでは男が生まれないため、成人として扱われる十六になると、子を作るために外の世界に男を探しに行く。村に男の存在がないわけではないが、外の世界から隔離されたような場所に定住しようなどと思う者は稀だ。ほとんどの娘は、子を宿した瞬間に男を捨てて村へ帰る。捨てる側のはずが逆に男を愛してその結果捨てられた母と私は違うから、男と交わるくらいなら子など要らないと思った。けれど、外の世界は別だ。十六になれば外に行くことを許される。私は、ずっと外へ行きたいと思っていた。
あと二年。十四になって間もないある日。森の中でいつものように民歌を歌っていると、そこへ一人の男がやってきた。黒いコートに身を包んだ、嫌なオーラを放つ男だった。念というものを知って二年。男の禍々しさが、強さがよく解って、すぐに身構えたけれど、男はそんなことは意にも介さずに私の意識を奪っていった。美しい声だ、と呟いて。
「おはよう、」
「……寝覚めにヒソカの顔は心臓に悪いよ」
三次試験が終わり、トリックタワーから出て今度は船に乗った。試験会場に着くまで時間があったので、飛行船や試験の後に休めなかった分仮眠をとっていたのだが、目を覚ましたの視界に飛び込んできたのは道化師ヒソカの白い顔だった。慣れているとはいえ、あまり寝起きに見たいものでもない。そもそも、いつから此処にいるのだろうか。
「そろそろ目的地に着くみたいだから、起きた方がいいよ?」
「それは、どうも……」
起き上がって、髪をかき上げようと腕を首の後ろに回して、ふと感じた違和感に顔を歪める。ああ、無いんだっけ。
クロロは長い髪が好きだった。何度も切ろうと思ったが、あいにく刃物を持たせてもらえなかったので自分で切ることは叶わなかった。子供の頃はずっと短髪だったのに、だいぶ彼の好みに染められていたようだ。
元来セルミアは外の世界へ行くことを前提としているため、言語は二種類勉強する。クロロの言葉も、全てではないけれど最初から理解はできていたが、言葉が通じないフリは三日で見抜かれてしまった。は六年間、容姿も言動も、全てクロロの好みを演じ続けた。それでいて、決して心は開かずに。だからクロロは余計にを欲して、縛り付けたくて、自由以外のあらゆるものを与えてきた。
早くおいでよ、そう言って背を向けて船の奥の方へと歩いて行ったヒソカを横目で見ながら、は軽い髪を掻きむしり呟く。
「……もう関係ない、か」
弱い母も、母を捨てた男も、には関係のないことだった。一族も、自分を育ててくれた長老のことも心配ではあるが一族そのものに執着はない。自由、望みはただそれだけだった。このままハンターライセンスが取れれば、蜘蛛から離れることが出来るだろうか。死なずに済むだろうか。そんなことを考えて、自嘲する。死に場所を求めて、あえてヒソカの提案に乗ってやったというのに、まさかまだ生を望むなんて。その理由は、何となくだけど察しはついていて、しかしだからこそ、口に出したくはなかった。
「……」
はポケットから一枚のカードを取り出すと、それを見つめた。三次試験の後、船に乗る前に引かされたそのクジには三桁の数字が刻まれていた。それが意味するのは、狩る者と狩られる者。即ち、このカードの番号が、自分のターゲットだと言うことだ。
404番。その数字の主を思い浮かべて、激しくなる鼓動をおさえるために深く息を吐いた。恐らく自分は、ここまでだ。
「応援するって、決めたじゃない……」
願えば願うほど、神は時として無慈悲だ。生きることすら望まなかった自分が、彼らと出会って未来を願った。仲間と言ってくれた人たちのために、役に立ちたいと思った。だからこそ、この試験に本気で臨むことは出来ないのだ。
「それじゃあ、また」
四次試験が行われるゼビル島では、三次試験のクリア順にスタートする。その分有利に事が運ぶわけだが、幸か不幸か三番目にクリアとなったはクラピカやゴン達にそう告げて森の中へと足を運んだ。
「やあ」
「何」
森へ入った瞬間、の目の前に立ち塞がるヒソカ。そういえば二番手はイルミだったので、彼相手にヒソカが隠れたりするわけもないだろうなと思った。だがいい加減しつこい相手にうんざりしつつ、一応用件を聞いてやる。やはりというべきか、相変わらずつまらない内容であった。
「キミのターゲット、誰だい?」
「なんでヒソカに言わないといけないの。教えるわけない」
「暇なんで、手伝ってあげようと思ってさ」
トランプを切りながら、一次試験の時のように暇だからと口にする。しかし、たとえ死んでもヒソカには頼りたくない。
「必要ない。私は一人で戦える」
「そう。……残念」
思ってもいないだろうに、そんなことを言うヒソカを無視して森の奥に足を進めた。どの道、この試験に受かる気はないのだ。
過去には海辺で暮らしていたこともあったらしいけれど、魔力のこもった歌声は船乗り達から忌み嫌われ、逃げるようにして森の奥深くに小さな集落を作り暮らすことを選んだ。当時の子供達は、誰に邪魔されることもなく、自由に歌を歌えた。私もその中の一人で、よく集落を抜け出して森の奥で歌っていた。観客は森と、そこに住む小動物たちだけ。あの男に会うまでは。
私は親の顔を知らない。父は外の男で、母は私を生んで間も無く死んだ。男に捨てられて自ら命を絶った愚かな女だと、一族の恥さらしと言われていた。よく知らないその人のことを、私は他人事のように聞いた。馬鹿な人だと。自分は、そんな風にはなりたくないと。
自害とは、最も愚かで罪深い行為だ。幼心に、強い女になりたいと強く思うようになったのだった。男に頼らずとも、私は生きていける。そう思った。
私の育ての親で一族の長老でもある婆様は、私が適齢期である十二になると念の存在を伝えた。歌を、オーラに込めて歌う方法を教えた。無差別に外の人間を襲っていた力を、制御する方法と、自由に歌うための力を学ばせてくれた。それでも外の世界は危険だからと子供達は森の外へ行くことは禁じられ、私はただひたすらに歌に願いを込めて歌った。そして、あの日も。
女系一族であるセルミアでは男が生まれないため、成人として扱われる十六になると、子を作るために外の世界に男を探しに行く。村に男の存在がないわけではないが、外の世界から隔離されたような場所に定住しようなどと思う者は稀だ。ほとんどの娘は、子を宿した瞬間に男を捨てて村へ帰る。捨てる側のはずが逆に男を愛してその結果捨てられた母と私は違うから、男と交わるくらいなら子など要らないと思った。けれど、外の世界は別だ。十六になれば外に行くことを許される。私は、ずっと外へ行きたいと思っていた。
あと二年。十四になって間もないある日。森の中でいつものように民歌を歌っていると、そこへ一人の男がやってきた。黒いコートに身を包んだ、嫌なオーラを放つ男だった。念というものを知って二年。男の禍々しさが、強さがよく解って、すぐに身構えたけれど、男はそんなことは意にも介さずに私の意識を奪っていった。美しい声だ、と呟いて。
「おはよう、」
「……寝覚めにヒソカの顔は心臓に悪いよ」
三次試験が終わり、トリックタワーから出て今度は船に乗った。試験会場に着くまで時間があったので、飛行船や試験の後に休めなかった分仮眠をとっていたのだが、目を覚ましたの視界に飛び込んできたのは道化師ヒソカの白い顔だった。慣れているとはいえ、あまり寝起きに見たいものでもない。そもそも、いつから此処にいるのだろうか。
「そろそろ目的地に着くみたいだから、起きた方がいいよ?」
「それは、どうも……」
起き上がって、髪をかき上げようと腕を首の後ろに回して、ふと感じた違和感に顔を歪める。ああ、無いんだっけ。
クロロは長い髪が好きだった。何度も切ろうと思ったが、あいにく刃物を持たせてもらえなかったので自分で切ることは叶わなかった。子供の頃はずっと短髪だったのに、だいぶ彼の好みに染められていたようだ。
元来セルミアは外の世界へ行くことを前提としているため、言語は二種類勉強する。クロロの言葉も、全てではないけれど最初から理解はできていたが、言葉が通じないフリは三日で見抜かれてしまった。は六年間、容姿も言動も、全てクロロの好みを演じ続けた。それでいて、決して心は開かずに。だからクロロは余計にを欲して、縛り付けたくて、自由以外のあらゆるものを与えてきた。
早くおいでよ、そう言って背を向けて船の奥の方へと歩いて行ったヒソカを横目で見ながら、は軽い髪を掻きむしり呟く。
「……もう関係ない、か」
弱い母も、母を捨てた男も、には関係のないことだった。一族も、自分を育ててくれた長老のことも心配ではあるが一族そのものに執着はない。自由、望みはただそれだけだった。このままハンターライセンスが取れれば、蜘蛛から離れることが出来るだろうか。死なずに済むだろうか。そんなことを考えて、自嘲する。死に場所を求めて、あえてヒソカの提案に乗ってやったというのに、まさかまだ生を望むなんて。その理由は、何となくだけど察しはついていて、しかしだからこそ、口に出したくはなかった。
「……」
はポケットから一枚のカードを取り出すと、それを見つめた。三次試験の後、船に乗る前に引かされたそのクジには三桁の数字が刻まれていた。それが意味するのは、狩る者と狩られる者。即ち、このカードの番号が、自分のターゲットだと言うことだ。
404番。その数字の主を思い浮かべて、激しくなる鼓動をおさえるために深く息を吐いた。恐らく自分は、ここまでだ。
「応援するって、決めたじゃない……」
願えば願うほど、神は時として無慈悲だ。生きることすら望まなかった自分が、彼らと出会って未来を願った。仲間と言ってくれた人たちのために、役に立ちたいと思った。だからこそ、この試験に本気で臨むことは出来ないのだ。
「それじゃあ、また」
四次試験が行われるゼビル島では、三次試験のクリア順にスタートする。その分有利に事が運ぶわけだが、幸か不幸か三番目にクリアとなったはクラピカやゴン達にそう告げて森の中へと足を運んだ。
「やあ」
「何」
森へ入った瞬間、の目の前に立ち塞がるヒソカ。そういえば二番手はイルミだったので、彼相手にヒソカが隠れたりするわけもないだろうなと思った。だがいい加減しつこい相手にうんざりしつつ、一応用件を聞いてやる。やはりというべきか、相変わらずつまらない内容であった。
「キミのターゲット、誰だい?」
「なんでヒソカに言わないといけないの。教えるわけない」
「暇なんで、手伝ってあげようと思ってさ」
トランプを切りながら、一次試験の時のように暇だからと口にする。しかし、たとえ死んでもヒソカには頼りたくない。
「必要ない。私は一人で戦える」
「そう。……残念」
思ってもいないだろうに、そんなことを言うヒソカを無視して森の奥に足を進めた。どの道、この試験に受かる気はないのだ。
to be continued...

- Back Top Next
