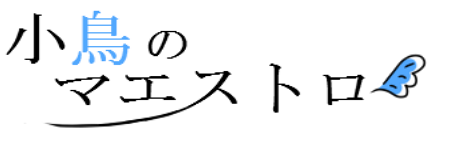

08

「は知ってる?」
「だから料理のことなんて知らないって。包丁も持ったことないんだから……キルア、刃をこっちに向けないでくれるかな」
「包丁持ったことないって、マジかよ。お前それで戦えんの?」
ニギリズシの作り方についてゴンに尋ねられ、更にはキルアに散々小馬鹿にされたは至極つまらなさそうな顔をして、調理場に背を向けた。どこへ? 仲間が尋ねると彼女は一言「パス」とだけ答えた。
「えっ、試験受けないの? 合格できないよ!?」
「……いいよ、別に。ゴン達は頑張って」
が拗ねて試験を放棄したと思ったゴンは、その原因であろうキルアを冷ややかな目で見た。彼にしては珍しいその視線に、居た堪れなくなったキルアは小さく「悪かったよ」と詫びたのだが、既にの姿はない。すぐに追いかけたところでこの試験に合格する糸口もない以上は呼び戻せないだろう。クラピカの発言もあり、一先ずは深追いするのは止めておこうという結論に達したのだが、の本音は別のところにあり、キルアに対しての怒りなどは微塵もないのである。
「……やあ、君も抜けてきたのかい?」
「うわ、間違えた」
「ちょっと待ちなよ」
人気のないところを選んで歩いて来たというのに、体中が毛羽立ちそうな声に呼ばれてはすぐさま引き返そうと踵を返した。が、奇術師には彼女が抱く嫌悪感などは伝わらず、音も無く腕を掴まれてしまった。
「君も諦めたんだろう? 今年の試験は」
「……別に。貴方と一緒にしないで」
ヒソカは去年、気に入らない試験管を半殺しにして失格した、と試験前にトンパが言っていたことを思い出す。現に今、目の前にいるヒソカは「あのままわけのわからない試験を続けられたら、また殺しちゃいそうだからさ」などと聞いてもいない理由をペラペラと喋った。しかし、ヒソカは来年、受けようと思えば自由に試験を受けられるのだ。彼がそこまで根気があるのかは別としておいて。だが、は違う。彼女にとってハンター試験とは、避難所なのだ。鳥籠から逃げるための、唯一の隠れ蓑だったのだ。即ちヒソカの言うハンター試験を諦めると言うことは、つまり「君は旅団の元に戻りたいのか」と尋ねているのだった。
ヒソカが自分を逃がすつもりが無いと悟ったは、諦めて少し離れた場所に腰を下ろす。川の水が、気持ちのいい音を立てる。まるで今がハンター試験中なんて嘘のようだ。
「試験がここで終わりだというなら、私も暴れてみようかな」
「君が? なんのために」
「……ハンターの人たちなら、上手に、殺してくれそうじゃない」
は死を望んでいるが、そのくせ自分で死ぬことを嫌がる。以前から、そんなに囚われの身でいるのが嫌なら自害でもしたらいいじゃないかとヒソカは彼女の絶望を最大限に煽ってきたし、実際にクロロに隠れて武器も渡した。しかし、それを実行しなかったのは、偏に彼女が「自ら命を絶つのは最も罪深いこと」だと認識しているからである。それが何故なのか、ヒソカにその理由までは語らずにいただったが、やはりその意思は今も健在のようだった。
「試験が終わるというのは、私の命が終わるということ。試験が終わって私が外に出れば、クロロが絶対にやってくる。良くて連れ戻しに、悪くて殺しに」
「……そうだろうね、その考えは正しいよ」
ヒソカはその修羅場が見たかったのと、その怒りがあわよくば連れ出した自分に向かないかと思っていたが、団員同士のマジギレはご法度というルールを頭が守らねば示しがつかないので、その線は薄い。となれば、目的はひとつしかない。狂気を孕んだクロロが彼女を閉じ込めて、また、彼女がどう抗っていくのか。両者が壊れていく、その過程を想像するだけでヒソカは震えが止まらなかった。
「なら、その前に誰かに殺してもらうの」
「じゃあ、僕が――」
「ヒソカは殺さないよ。殺さない」
「……」
「もし気が変わったとすれば、精々半殺しにしてクロロの元へ持って行くくらいでしょうね」
初めから殺す気なら、わざわざアジトから連れ出してハンター試験を受けさせるなんて回りくどいことはしないだろう。よくわかっている、とヒソカはまた心のそこから楽しそうに笑った。更に”連れて行く”ではなく”持って行く”と言い表した彼女は、自分のことも客観的に見て、クロロやヒソカが自分を人ではなく物として見ていることをしっかりと認識していた。だからこそ、ヒソカと言う奇術師はクロロがこのコレクションを愛して止まない理由が何となく想像ついたし、自分自身興味も沸いたのだ。あわよくば、その最期をクロロの代わりに自分が看取ってやりたいと思うくらいには。
「、君は……」
「何?」
「いや、なんでもないよ」
歯切れ悪いなあ、は溜息混じりに言う。そんな含み笑いは気味が悪いだけだよ、と。しかしヒソカはそれでも楽しそうに笑っていた。
、君はわかっているのかい?
自ら命を絶たずに誰かが手を下したからといって、それを自分の意思でそうなるように仕向けるなら、きっと同じことなのだ。自分で望んで死を選ぶなら、それは自害とどう違うというのだろうか。
本当に、面白い。ヒソカはより一層、笑みを深くした。
「じゃあ、君とももう少しでお別れなんだね。寂しくなるなあ」
「白々しい嘘吐かないでくれる? だからヒソカは嫌い」
酷いなとヒソカは口にしたが、本当に傷ついた様子はない。彼はその全てにおいて、存在自体が道化なのだ。や他の者が何を言ったとして、暖簾に腕押し、意味などない。
「僕が君を連れ出してあげたんじゃないか」
「頼んでないし、慈善事業じゃなくて嫌がらせに使っただけでしょう? 感謝する必要がどこにあるのかな」
「うーん、冷たいねぇ。マチみたいだ。ゾクゾクするよ」
「気持ち悪い……」
ヒソカの言うゾクゾクとは違う、悪寒に背筋が震えたは、すっくと立ち上がる。
「おや、どこへ?」
「……そろそろ戻る。おなかもすいた」
今までは、口にすればクロロは自由以外の全てを与えてくれた。だからこそ、困らせてやろうと無理難題を言うこともあったのだが、彼は諦めを知らない。どんなものでも必ず手に入れてしまうのだ。それがどんなに蛇の道であろうと、多くの者が死のうと関係がない。他人の屍の上で尚も美しく抗う女を愛で続けるために、多くの血に染まってきた。だからには、自分で何かをする必要もなかったのだ。
料理はしたことがない。戦うために刃を持つことはあっても包丁を持ったことがないのは本当だったが、それでも空腹の凌ぎ方くらいは知っている。川で魚をとって、焼けばいい。食べられる野草もいくつか知っている。幼い頃はよく森の中で遊んだものだ。
ヒソカは自分から離れようとするを、今度は追わなかった。話をして満足したのだろうか。終始、癇に障る笑い声が背中にまとわりついてくるようで本当に気持ち悪い。一刻も早く蜘蛛から解放されたいのに、結局はこの逃げ道も蜘蛛であるヒソカに用意されたものだと思うと本当に腹立たしかった。
「……あれ?」
森の中で木の実を見つけて、それらを胃におさめながら、そろそろ終わっているかもしれない試験会場に戻っている途中。低いプロペラ音と同時に影がさして、空を見上げる。
ハンター協会の印が描かれた飛行船が、試験会場を目指して飛んでいた。
「だから料理のことなんて知らないって。包丁も持ったことないんだから……キルア、刃をこっちに向けないでくれるかな」
「包丁持ったことないって、マジかよ。お前それで戦えんの?」
ニギリズシの作り方についてゴンに尋ねられ、更にはキルアに散々小馬鹿にされたは至極つまらなさそうな顔をして、調理場に背を向けた。どこへ? 仲間が尋ねると彼女は一言「パス」とだけ答えた。
「えっ、試験受けないの? 合格できないよ!?」
「……いいよ、別に。ゴン達は頑張って」
が拗ねて試験を放棄したと思ったゴンは、その原因であろうキルアを冷ややかな目で見た。彼にしては珍しいその視線に、居た堪れなくなったキルアは小さく「悪かったよ」と詫びたのだが、既にの姿はない。すぐに追いかけたところでこの試験に合格する糸口もない以上は呼び戻せないだろう。クラピカの発言もあり、一先ずは深追いするのは止めておこうという結論に達したのだが、の本音は別のところにあり、キルアに対しての怒りなどは微塵もないのである。
「……やあ、君も抜けてきたのかい?」
「うわ、間違えた」
「ちょっと待ちなよ」
人気のないところを選んで歩いて来たというのに、体中が毛羽立ちそうな声に呼ばれてはすぐさま引き返そうと踵を返した。が、奇術師には彼女が抱く嫌悪感などは伝わらず、音も無く腕を掴まれてしまった。
「君も諦めたんだろう? 今年の試験は」
「……別に。貴方と一緒にしないで」
ヒソカは去年、気に入らない試験管を半殺しにして失格した、と試験前にトンパが言っていたことを思い出す。現に今、目の前にいるヒソカは「あのままわけのわからない試験を続けられたら、また殺しちゃいそうだからさ」などと聞いてもいない理由をペラペラと喋った。しかし、ヒソカは来年、受けようと思えば自由に試験を受けられるのだ。彼がそこまで根気があるのかは別としておいて。だが、は違う。彼女にとってハンター試験とは、避難所なのだ。鳥籠から逃げるための、唯一の隠れ蓑だったのだ。即ちヒソカの言うハンター試験を諦めると言うことは、つまり「君は旅団の元に戻りたいのか」と尋ねているのだった。
ヒソカが自分を逃がすつもりが無いと悟ったは、諦めて少し離れた場所に腰を下ろす。川の水が、気持ちのいい音を立てる。まるで今がハンター試験中なんて嘘のようだ。
「試験がここで終わりだというなら、私も暴れてみようかな」
「君が? なんのために」
「……ハンターの人たちなら、上手に、殺してくれそうじゃない」
は死を望んでいるが、そのくせ自分で死ぬことを嫌がる。以前から、そんなに囚われの身でいるのが嫌なら自害でもしたらいいじゃないかとヒソカは彼女の絶望を最大限に煽ってきたし、実際にクロロに隠れて武器も渡した。しかし、それを実行しなかったのは、偏に彼女が「自ら命を絶つのは最も罪深いこと」だと認識しているからである。それが何故なのか、ヒソカにその理由までは語らずにいただったが、やはりその意思は今も健在のようだった。
「試験が終わるというのは、私の命が終わるということ。試験が終わって私が外に出れば、クロロが絶対にやってくる。良くて連れ戻しに、悪くて殺しに」
「……そうだろうね、その考えは正しいよ」
ヒソカはその修羅場が見たかったのと、その怒りがあわよくば連れ出した自分に向かないかと思っていたが、団員同士のマジギレはご法度というルールを頭が守らねば示しがつかないので、その線は薄い。となれば、目的はひとつしかない。狂気を孕んだクロロが彼女を閉じ込めて、また、彼女がどう抗っていくのか。両者が壊れていく、その過程を想像するだけでヒソカは震えが止まらなかった。
「なら、その前に誰かに殺してもらうの」
「じゃあ、僕が――」
「ヒソカは殺さないよ。殺さない」
「……」
「もし気が変わったとすれば、精々半殺しにしてクロロの元へ持って行くくらいでしょうね」
初めから殺す気なら、わざわざアジトから連れ出してハンター試験を受けさせるなんて回りくどいことはしないだろう。よくわかっている、とヒソカはまた心のそこから楽しそうに笑った。更に”連れて行く”ではなく”持って行く”と言い表した彼女は、自分のことも客観的に見て、クロロやヒソカが自分を人ではなく物として見ていることをしっかりと認識していた。だからこそ、ヒソカと言う奇術師はクロロがこのコレクションを愛して止まない理由が何となく想像ついたし、自分自身興味も沸いたのだ。あわよくば、その最期をクロロの代わりに自分が看取ってやりたいと思うくらいには。
「、君は……」
「何?」
「いや、なんでもないよ」
歯切れ悪いなあ、は溜息混じりに言う。そんな含み笑いは気味が悪いだけだよ、と。しかしヒソカはそれでも楽しそうに笑っていた。
、君はわかっているのかい?
自ら命を絶たずに誰かが手を下したからといって、それを自分の意思でそうなるように仕向けるなら、きっと同じことなのだ。自分で望んで死を選ぶなら、それは自害とどう違うというのだろうか。
本当に、面白い。ヒソカはより一層、笑みを深くした。
「じゃあ、君とももう少しでお別れなんだね。寂しくなるなあ」
「白々しい嘘吐かないでくれる? だからヒソカは嫌い」
酷いなとヒソカは口にしたが、本当に傷ついた様子はない。彼はその全てにおいて、存在自体が道化なのだ。や他の者が何を言ったとして、暖簾に腕押し、意味などない。
「僕が君を連れ出してあげたんじゃないか」
「頼んでないし、慈善事業じゃなくて嫌がらせに使っただけでしょう? 感謝する必要がどこにあるのかな」
「うーん、冷たいねぇ。マチみたいだ。ゾクゾクするよ」
「気持ち悪い……」
ヒソカの言うゾクゾクとは違う、悪寒に背筋が震えたは、すっくと立ち上がる。
「おや、どこへ?」
「……そろそろ戻る。おなかもすいた」
今までは、口にすればクロロは自由以外の全てを与えてくれた。だからこそ、困らせてやろうと無理難題を言うこともあったのだが、彼は諦めを知らない。どんなものでも必ず手に入れてしまうのだ。それがどんなに蛇の道であろうと、多くの者が死のうと関係がない。他人の屍の上で尚も美しく抗う女を愛で続けるために、多くの血に染まってきた。だからには、自分で何かをする必要もなかったのだ。
料理はしたことがない。戦うために刃を持つことはあっても包丁を持ったことがないのは本当だったが、それでも空腹の凌ぎ方くらいは知っている。川で魚をとって、焼けばいい。食べられる野草もいくつか知っている。幼い頃はよく森の中で遊んだものだ。
ヒソカは自分から離れようとするを、今度は追わなかった。話をして満足したのだろうか。終始、癇に障る笑い声が背中にまとわりついてくるようで本当に気持ち悪い。一刻も早く蜘蛛から解放されたいのに、結局はこの逃げ道も蜘蛛であるヒソカに用意されたものだと思うと本当に腹立たしかった。
「……あれ?」
森の中で木の実を見つけて、それらを胃におさめながら、そろそろ終わっているかもしれない試験会場に戻っている途中。低いプロペラ音と同時に影がさして、空を見上げる。
ハンター協会の印が描かれた飛行船が、試験会場を目指して飛んでいた。
to be continued...

- Back Top Next
