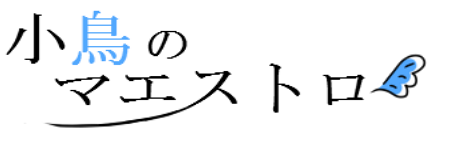

07

ヒソカが去ってからややしばらく経つと、ゴンとクラピカの姿が見えた。
特に心配はしていなかったが、どうやってここまで来たか尋ねれば、ゴンはレオリオを指差して「香水の匂いだよ」と言った。相変わらず人間離れした能力だと思うと同時に、は素直に感心する。
「それよりも、ヒソカと知り合いだったのだな。大丈夫だったのか?」
「……少し話しただけだよ。関わりたくはないんだけど、一応知り合いっていうか……まあ、そんなとこ」
歯切れの悪いだったが、詮索してほしくは無いことのようでクラピカから視線を外す。すると、そこでレオリオが目を覚ました。
「俺、なんでこんな怪我してんだ? どうも湿原に入った後の記憶が曖昧でよ」
「……」
本当のことは言わないでおこう。レオリオの大きく腫れ上がった頬を見つめながら、三人はそう誓うのだった。
「でも、なんでみんな建物の外にいるの?」
「さあ……ずっとレオリオについていたから」
「入れないんだよ、ほら。貼紙があるだろ」
人だかりの理由が解らずに正直に伝えれば、背後から質問の答えが返ってくる。振り返って声の方を見れば、ゴンと一緒に走っていた銀髪の少年がスケボーを抱えてやってきた。
「キルア! ……えっと、貼紙?」
ゴンが嬉しそうに少年の名を呼ぶ。そこで、は少年の名前を知った。
扉には、大きく"本日正午、二次試験スタート"とだけ書いてあった。あと五分ほどでその時間ではあるが、扉の奥からは何とも形容しがたい地響きすら含んだ唸り声のような音が聞こえてくる。その唸り声に警戒する周囲の受験生達であったが、はどことなく"正午"という時間帯が気になっていた。
「……お昼休憩はなしか」
小さなの呟きは扉奥から聞こえてくる唸り声にかき消された。
ひたすら走ったりヒソカに捕まったりと意識がそちらへ向いていたため今まで気にしていなかったが、一次試験を通過して気持ちが落ち着いてくると何となく空腹感がある。間も無く二次試験が始まり、一次試験の時間から考えてもすぐに終わる試験でもないだろう。
建物の上に備え付けられた時計の両の針が真上を指し、自動式らしい扉がゆっくりと開いていく。ごくり、と誰のものかわからない唾を飲み込む音が聞こえてきた。
扉の中にいたのは、ソファに腰掛けた女と山のようなシルエットの巨漢だった。
「どう? お腹は大分すいてきた?」
「聞いての通り、もうペコペコだよ……」
どうやら、唸り声だと思っていたのは彼の腹の虫らしい。そんなやり取りを聞きながら全員の表情が強張る。
まさか、そんな試験が、
「そんなわけで、二次試験は料理よ!」
「……!?」
そのまさかである。
「湿原には詐欺師がたくさんいて、森には豚がたくさんいるんだね」
「そんな暢気なことを言っている場合か?」
二人の試験管それぞれが指定する料理を作る、という内容はわかりやすいものだったが、周囲の雰囲気から察するに料理をしたことがない連中が多い様子。クラピカも例外ではないので、女であるに視線だけでどうだと問えば、彼女は薄ら笑みを浮かべて首を横に振ったのだった。
「……そうか」
少しだけ残念そうな表情を浮かべるクラピカに、は小さく嘆息する。残念なのは自分もだ。幼い頃にもう少し家事手伝いをしておけば良かったと後悔しても遅い。
女が皆料理をするわけでは勿論ない。それに、料理をするからと言って上手なわけでもない。は包丁に触れたことすらなかったが、旅団の中で料理と言う名の創作毒物を生み出す二人の女のことを思い出してさあっと顔を青くした。
「あの時は死にかけた……」
「?」
「なんでもない」
素早く逃げ去った男性団員達を尻目に、味見と称して毒物投与された。あのときばかりは、必死な顔で解毒剤を盗ってきたクロロが神に見えた。しかし今作るべきなのは、毒ではなく料理だ。思い出すのは彼女たちではない。
「あ、いたよ!」
ゴンが嬉々として声を上げる。そこに居たのは通常の豚の何倍もの大きさの豚だった。どうやら湿原の動物と同様に好戦的な性格のようで、真っ直ぐに突進してくる巨大な豚。だが注目すべきは、その大きく尖った鼻である。
「何あれ、ねぇクラピカ知ってる?」
「いや……」
本の虫で図鑑や歴史書などあらゆる書物を読み漁るクラピカのことだから、見たことのない不思議な生物についても知っているかと思いきや、意外にも彼は先ほどのと同じく首を振ったのだった。
お互いに顔を見合わせると、獰猛な動物を前にしているというのに緊張感もなく頬が緩むのを感じた。
「お互いまだまだだねぇ」
「確かにな」
森の中では100名以上もの受験生が豚を捕らえようと走り回っている。しかし聞こえてくるのは豚が木や岩に衝突しているような轟音で、それと同時にいくつかの悲鳴も上がっていた。
そんなに慌ただしくしなくても、きっとこの狩はとても簡単なもののはずなのに。
「……やった!」
「ナイスだ、ゴン!」
ゴンが釣竿で豚の額を突けば、その巨体はあっけなく真横に崩れた。巨大な鼻は脆い額をガードするための進化というわけで、つまりはそれさえ見抜いてしまえば楽なものだ。
あまり気乗りはしないのだけれど、それでも自分が生きていくためには致し方のないことで、小さく心の中で謝罪する。ごめんね、食べるのは私じゃないけれど――生贄になって。
静かな動作で豚の突進をかわす。大木にぶつかって動きを止めた豚は、それはそれは隙だらけで。豚が体当たりをしたことで、腐りかけた枝がぐらりと折れて傾いた。風を使ってその枝を切り離してやったは、目を閉じて両の手を合わせた。
「も倒したんだね、良かった!」
「……でもまだ、倒しただけだし。焼くためには火を熾さないと」
それには及ばない、という声に振り向けば、先に豚を仕留めていたクラピカとレオリオが既に火の用意をしていた。クラピカのことだから火の熾し方は完璧だろうし、火種はレオリオがマッチを持っていたから何も問題はなかった。クラピカの指示でせっせと動くレオリオやゴンの姿を見ながら、ただようやく一体の豚を倒しただけのは愕然とした。自分は本当に無知なのだと。
「ほら早く、の豚も焼かないと!」
「う、うん。でも――多分それまだ焼いた方がいいよ。生焼け。あとレオリオは焼きすぎだと思う」
気持ちが急いているのだろうか。既に何名かは森を抜けて豚を運んでいたようであったし、もしかすると試食は始まっているのかもしれない。だが、どう素人目に見てもゴンの豚は火が通っていないし、レオリオのは大分焦げていた。
「い、いいんだよ細かいことは! ……ほら、さっさと焼いて持って行こうぜ!」
「はいはい」
そんなに急ぐ必要はないと思うが、早いに越したことはない。何とか豚を焼き上げて、急いで二次試験会場まで戻ると、そこには大量の焼き豚が並んでいた。
その数、七十。女にブハラと呼ばれたその男は、とても幸せそうな顔で豚の丸焼きを胃におさめていく。美味い美味いと全ての豚をそう評しながら、特に味わう様子もなく、またレオリオが持ってきたような黒焦げの豚すらも喜んで食べていた。
「あー、食った食った。お腹いっぱい」
結局、並べられた全ての豚を食べたブハラに、一同は驚愕した。彼の腹のおかげで豚を仕留めてきた全員が合格となったわけだが、それでも恐ろしいものがある。
ハンターってすごいんだね、ゴンの見当違いな感想が聞こえた。
「でも、次はこうはいかないわよ」
満腹のブハラに呆れつつ、女性試験管のメンチが次の課題を宣言する。
「次の料理は、スシよ!」
それは聞いたこともない名前だった。
特に心配はしていなかったが、どうやってここまで来たか尋ねれば、ゴンはレオリオを指差して「香水の匂いだよ」と言った。相変わらず人間離れした能力だと思うと同時に、は素直に感心する。
「それよりも、ヒソカと知り合いだったのだな。大丈夫だったのか?」
「……少し話しただけだよ。関わりたくはないんだけど、一応知り合いっていうか……まあ、そんなとこ」
歯切れの悪いだったが、詮索してほしくは無いことのようでクラピカから視線を外す。すると、そこでレオリオが目を覚ました。
「俺、なんでこんな怪我してんだ? どうも湿原に入った後の記憶が曖昧でよ」
「……」
本当のことは言わないでおこう。レオリオの大きく腫れ上がった頬を見つめながら、三人はそう誓うのだった。
「でも、なんでみんな建物の外にいるの?」
「さあ……ずっとレオリオについていたから」
「入れないんだよ、ほら。貼紙があるだろ」
人だかりの理由が解らずに正直に伝えれば、背後から質問の答えが返ってくる。振り返って声の方を見れば、ゴンと一緒に走っていた銀髪の少年がスケボーを抱えてやってきた。
「キルア! ……えっと、貼紙?」
ゴンが嬉しそうに少年の名を呼ぶ。そこで、は少年の名前を知った。
扉には、大きく"本日正午、二次試験スタート"とだけ書いてあった。あと五分ほどでその時間ではあるが、扉の奥からは何とも形容しがたい地響きすら含んだ唸り声のような音が聞こえてくる。その唸り声に警戒する周囲の受験生達であったが、はどことなく"正午"という時間帯が気になっていた。
「……お昼休憩はなしか」
小さなの呟きは扉奥から聞こえてくる唸り声にかき消された。
ひたすら走ったりヒソカに捕まったりと意識がそちらへ向いていたため今まで気にしていなかったが、一次試験を通過して気持ちが落ち着いてくると何となく空腹感がある。間も無く二次試験が始まり、一次試験の時間から考えてもすぐに終わる試験でもないだろう。
建物の上に備え付けられた時計の両の針が真上を指し、自動式らしい扉がゆっくりと開いていく。ごくり、と誰のものかわからない唾を飲み込む音が聞こえてきた。
扉の中にいたのは、ソファに腰掛けた女と山のようなシルエットの巨漢だった。
「どう? お腹は大分すいてきた?」
「聞いての通り、もうペコペコだよ……」
どうやら、唸り声だと思っていたのは彼の腹の虫らしい。そんなやり取りを聞きながら全員の表情が強張る。
まさか、そんな試験が、
「そんなわけで、二次試験は料理よ!」
「……!?」
そのまさかである。
「湿原には詐欺師がたくさんいて、森には豚がたくさんいるんだね」
「そんな暢気なことを言っている場合か?」
二人の試験管それぞれが指定する料理を作る、という内容はわかりやすいものだったが、周囲の雰囲気から察するに料理をしたことがない連中が多い様子。クラピカも例外ではないので、女であるに視線だけでどうだと問えば、彼女は薄ら笑みを浮かべて首を横に振ったのだった。
「……そうか」
少しだけ残念そうな表情を浮かべるクラピカに、は小さく嘆息する。残念なのは自分もだ。幼い頃にもう少し家事手伝いをしておけば良かったと後悔しても遅い。
女が皆料理をするわけでは勿論ない。それに、料理をするからと言って上手なわけでもない。は包丁に触れたことすらなかったが、旅団の中で料理と言う名の創作毒物を生み出す二人の女のことを思い出してさあっと顔を青くした。
「あの時は死にかけた……」
「?」
「なんでもない」
素早く逃げ去った男性団員達を尻目に、味見と称して毒物投与された。あのときばかりは、必死な顔で解毒剤を盗ってきたクロロが神に見えた。しかし今作るべきなのは、毒ではなく料理だ。思い出すのは彼女たちではない。
「あ、いたよ!」
ゴンが嬉々として声を上げる。そこに居たのは通常の豚の何倍もの大きさの豚だった。どうやら湿原の動物と同様に好戦的な性格のようで、真っ直ぐに突進してくる巨大な豚。だが注目すべきは、その大きく尖った鼻である。
「何あれ、ねぇクラピカ知ってる?」
「いや……」
本の虫で図鑑や歴史書などあらゆる書物を読み漁るクラピカのことだから、見たことのない不思議な生物についても知っているかと思いきや、意外にも彼は先ほどのと同じく首を振ったのだった。
お互いに顔を見合わせると、獰猛な動物を前にしているというのに緊張感もなく頬が緩むのを感じた。
「お互いまだまだだねぇ」
「確かにな」
森の中では100名以上もの受験生が豚を捕らえようと走り回っている。しかし聞こえてくるのは豚が木や岩に衝突しているような轟音で、それと同時にいくつかの悲鳴も上がっていた。
そんなに慌ただしくしなくても、きっとこの狩はとても簡単なもののはずなのに。
「……やった!」
「ナイスだ、ゴン!」
ゴンが釣竿で豚の額を突けば、その巨体はあっけなく真横に崩れた。巨大な鼻は脆い額をガードするための進化というわけで、つまりはそれさえ見抜いてしまえば楽なものだ。
あまり気乗りはしないのだけれど、それでも自分が生きていくためには致し方のないことで、小さく心の中で謝罪する。ごめんね、食べるのは私じゃないけれど――生贄になって。
静かな動作で豚の突進をかわす。大木にぶつかって動きを止めた豚は、それはそれは隙だらけで。豚が体当たりをしたことで、腐りかけた枝がぐらりと折れて傾いた。風を使ってその枝を切り離してやったは、目を閉じて両の手を合わせた。
「も倒したんだね、良かった!」
「……でもまだ、倒しただけだし。焼くためには火を熾さないと」
それには及ばない、という声に振り向けば、先に豚を仕留めていたクラピカとレオリオが既に火の用意をしていた。クラピカのことだから火の熾し方は完璧だろうし、火種はレオリオがマッチを持っていたから何も問題はなかった。クラピカの指示でせっせと動くレオリオやゴンの姿を見ながら、ただようやく一体の豚を倒しただけのは愕然とした。自分は本当に無知なのだと。
「ほら早く、の豚も焼かないと!」
「う、うん。でも――多分それまだ焼いた方がいいよ。生焼け。あとレオリオは焼きすぎだと思う」
気持ちが急いているのだろうか。既に何名かは森を抜けて豚を運んでいたようであったし、もしかすると試食は始まっているのかもしれない。だが、どう素人目に見てもゴンの豚は火が通っていないし、レオリオのは大分焦げていた。
「い、いいんだよ細かいことは! ……ほら、さっさと焼いて持って行こうぜ!」
「はいはい」
そんなに急ぐ必要はないと思うが、早いに越したことはない。何とか豚を焼き上げて、急いで二次試験会場まで戻ると、そこには大量の焼き豚が並んでいた。
その数、七十。女にブハラと呼ばれたその男は、とても幸せそうな顔で豚の丸焼きを胃におさめていく。美味い美味いと全ての豚をそう評しながら、特に味わう様子もなく、またレオリオが持ってきたような黒焦げの豚すらも喜んで食べていた。
「あー、食った食った。お腹いっぱい」
結局、並べられた全ての豚を食べたブハラに、一同は驚愕した。彼の腹のおかげで豚を仕留めてきた全員が合格となったわけだが、それでも恐ろしいものがある。
ハンターってすごいんだね、ゴンの見当違いな感想が聞こえた。
「でも、次はこうはいかないわよ」
満腹のブハラに呆れつつ、女性試験管のメンチが次の課題を宣言する。
「次の料理は、スシよ!」
それは聞いたこともない名前だった。
to be continued...

- Back Top Next
