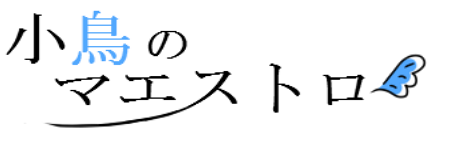

Episode.02 その傷 の所有主は

背中を這う指が気持ち悪くて、わざと自分の左腕の皮膚を噛み千切ったことがある。
奴もまさか私がそんな行動を取るとは予想していなかったようで、無表情ながらにも動揺しているのがわかって可笑しかった。私の力では奴に傷ひとつ負わせられないのは初めから理解していたし、ならば奴が大事にしているコレクションを破壊してやればいい。我ながら妙案だとすら思った。
そんな私を彼は責めることもせず、行為を中断して何も言わずに手当てをした。私も黙ってそれを受け入れて、静かに言ってやったのだ。
「次は舌を噛んでやる」と。
それ以来、クロロが強硬手段に出ることはなくなった。けれど、それでもクロロに無関心で居続けた私を、クロロは面白くは思わないだろう。彼のいない間の世話係としてパクノダやシャルナーク、他の団員とはそれなりに交わす言葉すらクロロの前では全て呑み込んだ。しかしクロロは辛抱強く、私に言葉をかけ続けた。生けるコレクションだなんて言うけれど、自分の思い通りにならない装飾品など、とても無意味なものでしかないのに。よくもまあ、辛抱強くいられるものだと他人事のように思った。
私が彼に抱く感情は憎悪でも恐怖でもない。ただただ、早く飽きて捨てられたい。私が彼に少しでも感心を示したものなら、恐らくもう一生解放してはもらえないのだ。その結果が死であったとしても別に良かった。目の前で自ら命を絶ってやろうかと考えたこともあったが、それも違うような気がして止めた。
そのかわりに、私は抵抗を続けた。クロロを呆れさせるように、怒らせるように、私への感心を失くすように。
「美しいな」
クロロがそう言った一族の証を、私は躊躇い無く破壊した。
「……夢か」
昨夜は町へ着かず、森の中で野宿をしたことを思い出す。自分は夜目がきくから大丈夫だと言ったのだが、頭の固いクラピカがダメの一点張りで、結局そこで夜を明かした。
クラピカの姿は既に無い。恐らくは辺りを散策でもしているのだろうが、今顔を合わせなくて良かったと安堵する。
耳を澄ませば聞こえてくる水音に、沢があることを知る。実は昨晩から聞こえていたが、疲れていたのかすぐに眠りに入ってしまったのだった。
「顔、洗ってくるかな……」
そう遠くない過去の夢を見たことで、暫く忘れていた――否、忘れていたかった不快感がせり上がってくる。クラピカが戻ってくる前に行ってこようとは立ち上がり水音のする方へと歩いて行った。
沢の水を掌で掬いながら、水面に映った自分の顔に溜息を吐く。
「ひっどい顔」
特に悲しかった記憶は無かったのに、夢の中で泣いたのだろうか。目が赤く、疲れきった顔の自分がそこにはいた。
掬った水で顔を洗う。ひやりと冷たい水が頭の芯をしゃっきりさせてくれる。
「……消えないな」
水を掬うために持ち上げた腕を見てそう呟く。
身体のあちこちについた、クロロを拒む度に増えた傷たち。その中でも一番大きなものはやはり、
「あっ」
体重をかけすぎたのか、手をかけていた岩場が突然崩れた。いや、ぬかるみで手が滑ったのだ。前のめりになっていた身体が浮いて、気がつけば水面に沈んでいた。
「……あーあ、気持ち悪い」
沢が浅いおかげで特に外傷はなかったが、すっかり服が水分を吸い上げて重みを増していた。
水から上がると、靴を脱いで水を出す。それから上の服を脱ぐ。ゆっくり雑巾の水を絞る要領で衣服を捻っていくと、大量の水が滴り落ちていく。出発までに乾けばいいけれど、とぼんやり考える。
中に来ていた肩紐の細いキャミソールも少しは濡れたが、流石に全て脱ぐのは躊躇われる。近くにクラピカがいるかもしれないのだ。何かあるわけではないが、一応そこは考慮に入れておく。それに、あまり見せられたものでもない。
「?」
「……あ」
「!? な、何をしているのだ」
運悪くと言うべきかタイミング良くと言うべきか、そこへクラピカが現れたが、の格好を見て慌てて視線を逸らした。
「水に落ちて、濡れた」
「……それは、見ればわかるが……」
そもそも、動転して何をしているのだと尋ねたのはクラピカの方であった。普段から露出の控えた服を着ている彼女であるからか、こうして肌を晒しているとどうしても目のやり場に困ってしまうのだ。
先に戻っていると伝えようと口を開きかけたクラピカだったが、目の端に映ったものに、動きを止める。
「……その、傷は」
「……ああ、これね」
彼女の背中にある、大きな刺し傷に目を離せなくなる。
は溜息をひとつ吐くと、クラピカに向き直った。
「私が私のものだという、証だよ」
は荷物の中から適当な着替えを引っ張り出すと更衣を済ませ、火を焚いてくれていたクラピカの元へと向う。
クラピカと向かい合う形で座ったは、ゆっくりと口を開いた。
「私は、セルミア一族の一人。セルミアはセイレーンの子孫と、言われている」
「セイレーン……神話に出てくる、あの物の怪のか?」
「そう。美しい歌声で船乗りを惑わせる、幻獣のこと。相変わらず博識で助かるよ」
この傷の下にある二つの痣は、過去に祖先が人として生きるために捨てた翼の痕だと言い伝えられている。
「その傷は、誰かに……?」
は静かに、首を振る。クラピカは目を見開いた。先日の野党のように、追剥連中にやられたものだと思ったからだ。
「自分でつけた」
「何故」
は、言うべきか言わざるべきか迷った。
物知りのクラピカのことだ、恐らく幻影旅団という名前を出せばそれがどんな連中かもすぐに解ってしまうだろう。そんな奴らに追われていると知れば、きっともう一緒にはいられない。そう思ったはあえて名を伏せて話しをした。試験中は邪魔が入ることはないのだから、試験が終わってから自分から離れれば良いのだと、そう言い聞かせて。
「その一族には、声に魔力が宿っていると信じられているから。死ねば声は嗄れてしまうし、私達は生きているからこそ価値がある」
「……」
「私は自分で、私の価値を失うように仕向けてきた。私に人を殺すだけの力量はないから、それしかわからなかった」
クラピカは黙ったまま、の話に耳を傾けていた。
「この前、野党を追い払ったのもその力だよ。私の声には自然に干渉する力がある。……ただそれだけなのにね」
あの時のクロロの顔が忘れられない。思い出すたびに、笑いがこみ上げてくる。もっと、もっと傷つけばいい。この背中の傷と同じくらいかそれ以上に、クロロの心に傷が残ることを望んだ。
背中の代わりに腕についた傷を慈しむように撫で付けるを見ながら、何を思ったのか今度はクラピカが口を開く。
「私は、クルタ族だ」
フェアじゃないと、思ったからだろうか。過去を話すことに何の躊躇いもないだったが、可笑しそうに笑うの姿が彼には狂っているように見えたのかもしれない。
クルタ族。聞いたことがあるようなないような、とは考えをめぐらせた。ぼんやりと、思い出せない。
「クルタ族は、幻影旅団に虐殺された」
「……っ!」
そう言ったクラピカが顔を上げると、そこにあったのはいつもの彼の色ではない。茶色がかった瞳は色を変え、鮮やかな緋の光を放っていた。
「感情が高ぶると、鮮やかな緋色に変わる。……緋の眼と呼ばれ、世界七大美色に数えられているほどだ」
そこでは――は思い出した。
ほら綺麗だろう、とクロロが以前の元に一対の緋の眼を持ってきたことがあった。興味が無いと突っぱねつつも、クロロは彼女が心の奥底で死に恐怖しているのを知っていた。次はお前の番だといわれているようで、恐ろしかったのだ。自分への興味が無くなれば、きっと躊躇うことなくクロロはその命すら奪うだろう。
「私はハンター試験に合格し、幻影旅団に復讐する」
「……そう」
クラピカに旅団の名前を出さなかったことは、偶然だったとは言え良かったとは安堵した。幻影旅団に復讐するという目的を持つクラピカと、奴らから逃げ延びたいとではその目的は完全に似て非なるものだった。
だからハンター試験が終われば、それ以上一緒にいるわけにはいかなかった。
「は、ハンターになったらどうするのだ?」
「え?」
「いや、無粋な質問だったな。すまない。……自由に、なったのだからな」
「……うん、そうだね、私は自由に……なりたかったから」
しかしそれは期限付きの自由でしかない。
本当の意味で自由になれないことは、自分自身が誰よりも理解していた。
それを知っていたからこそヒソカは、を檻の外から逃がしたのだ。飼い主が迎えに来ることを見越して。
――私は、死にたいと思ったんだよ。
そんなこと、この人の前では言えないなと、そう思っただった。
奴もまさか私がそんな行動を取るとは予想していなかったようで、無表情ながらにも動揺しているのがわかって可笑しかった。私の力では奴に傷ひとつ負わせられないのは初めから理解していたし、ならば奴が大事にしているコレクションを破壊してやればいい。我ながら妙案だとすら思った。
そんな私を彼は責めることもせず、行為を中断して何も言わずに手当てをした。私も黙ってそれを受け入れて、静かに言ってやったのだ。
「次は舌を噛んでやる」と。
それ以来、クロロが強硬手段に出ることはなくなった。けれど、それでもクロロに無関心で居続けた私を、クロロは面白くは思わないだろう。彼のいない間の世話係としてパクノダやシャルナーク、他の団員とはそれなりに交わす言葉すらクロロの前では全て呑み込んだ。しかしクロロは辛抱強く、私に言葉をかけ続けた。生けるコレクションだなんて言うけれど、自分の思い通りにならない装飾品など、とても無意味なものでしかないのに。よくもまあ、辛抱強くいられるものだと他人事のように思った。
私が彼に抱く感情は憎悪でも恐怖でもない。ただただ、早く飽きて捨てられたい。私が彼に少しでも感心を示したものなら、恐らくもう一生解放してはもらえないのだ。その結果が死であったとしても別に良かった。目の前で自ら命を絶ってやろうかと考えたこともあったが、それも違うような気がして止めた。
そのかわりに、私は抵抗を続けた。クロロを呆れさせるように、怒らせるように、私への感心を失くすように。
「美しいな」
クロロがそう言った一族の証を、私は躊躇い無く破壊した。
「……夢か」
昨夜は町へ着かず、森の中で野宿をしたことを思い出す。自分は夜目がきくから大丈夫だと言ったのだが、頭の固いクラピカがダメの一点張りで、結局そこで夜を明かした。
クラピカの姿は既に無い。恐らくは辺りを散策でもしているのだろうが、今顔を合わせなくて良かったと安堵する。
耳を澄ませば聞こえてくる水音に、沢があることを知る。実は昨晩から聞こえていたが、疲れていたのかすぐに眠りに入ってしまったのだった。
「顔、洗ってくるかな……」
そう遠くない過去の夢を見たことで、暫く忘れていた――否、忘れていたかった不快感がせり上がってくる。クラピカが戻ってくる前に行ってこようとは立ち上がり水音のする方へと歩いて行った。
沢の水を掌で掬いながら、水面に映った自分の顔に溜息を吐く。
「ひっどい顔」
特に悲しかった記憶は無かったのに、夢の中で泣いたのだろうか。目が赤く、疲れきった顔の自分がそこにはいた。
掬った水で顔を洗う。ひやりと冷たい水が頭の芯をしゃっきりさせてくれる。
「……消えないな」
水を掬うために持ち上げた腕を見てそう呟く。
身体のあちこちについた、クロロを拒む度に増えた傷たち。その中でも一番大きなものはやはり、
「あっ」
体重をかけすぎたのか、手をかけていた岩場が突然崩れた。いや、ぬかるみで手が滑ったのだ。前のめりになっていた身体が浮いて、気がつけば水面に沈んでいた。
「……あーあ、気持ち悪い」
沢が浅いおかげで特に外傷はなかったが、すっかり服が水分を吸い上げて重みを増していた。
水から上がると、靴を脱いで水を出す。それから上の服を脱ぐ。ゆっくり雑巾の水を絞る要領で衣服を捻っていくと、大量の水が滴り落ちていく。出発までに乾けばいいけれど、とぼんやり考える。
中に来ていた肩紐の細いキャミソールも少しは濡れたが、流石に全て脱ぐのは躊躇われる。近くにクラピカがいるかもしれないのだ。何かあるわけではないが、一応そこは考慮に入れておく。それに、あまり見せられたものでもない。
「?」
「……あ」
「!? な、何をしているのだ」
運悪くと言うべきかタイミング良くと言うべきか、そこへクラピカが現れたが、の格好を見て慌てて視線を逸らした。
「水に落ちて、濡れた」
「……それは、見ればわかるが……」
そもそも、動転して何をしているのだと尋ねたのはクラピカの方であった。普段から露出の控えた服を着ている彼女であるからか、こうして肌を晒しているとどうしても目のやり場に困ってしまうのだ。
先に戻っていると伝えようと口を開きかけたクラピカだったが、目の端に映ったものに、動きを止める。
「……その、傷は」
「……ああ、これね」
彼女の背中にある、大きな刺し傷に目を離せなくなる。
は溜息をひとつ吐くと、クラピカに向き直った。
「私が私のものだという、証だよ」
は荷物の中から適当な着替えを引っ張り出すと更衣を済ませ、火を焚いてくれていたクラピカの元へと向う。
クラピカと向かい合う形で座ったは、ゆっくりと口を開いた。
「私は、セルミア一族の一人。セルミアはセイレーンの子孫と、言われている」
「セイレーン……神話に出てくる、あの物の怪のか?」
「そう。美しい歌声で船乗りを惑わせる、幻獣のこと。相変わらず博識で助かるよ」
この傷の下にある二つの痣は、過去に祖先が人として生きるために捨てた翼の痕だと言い伝えられている。
「その傷は、誰かに……?」
は静かに、首を振る。クラピカは目を見開いた。先日の野党のように、追剥連中にやられたものだと思ったからだ。
「自分でつけた」
「何故」
は、言うべきか言わざるべきか迷った。
物知りのクラピカのことだ、恐らく幻影旅団という名前を出せばそれがどんな連中かもすぐに解ってしまうだろう。そんな奴らに追われていると知れば、きっともう一緒にはいられない。そう思ったはあえて名を伏せて話しをした。試験中は邪魔が入ることはないのだから、試験が終わってから自分から離れれば良いのだと、そう言い聞かせて。
「その一族には、声に魔力が宿っていると信じられているから。死ねば声は嗄れてしまうし、私達は生きているからこそ価値がある」
「……」
「私は自分で、私の価値を失うように仕向けてきた。私に人を殺すだけの力量はないから、それしかわからなかった」
クラピカは黙ったまま、の話に耳を傾けていた。
「この前、野党を追い払ったのもその力だよ。私の声には自然に干渉する力がある。……ただそれだけなのにね」
あの時のクロロの顔が忘れられない。思い出すたびに、笑いがこみ上げてくる。もっと、もっと傷つけばいい。この背中の傷と同じくらいかそれ以上に、クロロの心に傷が残ることを望んだ。
背中の代わりに腕についた傷を慈しむように撫で付けるを見ながら、何を思ったのか今度はクラピカが口を開く。
「私は、クルタ族だ」
フェアじゃないと、思ったからだろうか。過去を話すことに何の躊躇いもないだったが、可笑しそうに笑うの姿が彼には狂っているように見えたのかもしれない。
クルタ族。聞いたことがあるようなないような、とは考えをめぐらせた。ぼんやりと、思い出せない。
「クルタ族は、幻影旅団に虐殺された」
「……っ!」
そう言ったクラピカが顔を上げると、そこにあったのはいつもの彼の色ではない。茶色がかった瞳は色を変え、鮮やかな緋の光を放っていた。
「感情が高ぶると、鮮やかな緋色に変わる。……緋の眼と呼ばれ、世界七大美色に数えられているほどだ」
そこでは――は思い出した。
ほら綺麗だろう、とクロロが以前の元に一対の緋の眼を持ってきたことがあった。興味が無いと突っぱねつつも、クロロは彼女が心の奥底で死に恐怖しているのを知っていた。次はお前の番だといわれているようで、恐ろしかったのだ。自分への興味が無くなれば、きっと躊躇うことなくクロロはその命すら奪うだろう。
「私はハンター試験に合格し、幻影旅団に復讐する」
「……そう」
クラピカに旅団の名前を出さなかったことは、偶然だったとは言え良かったとは安堵した。幻影旅団に復讐するという目的を持つクラピカと、奴らから逃げ延びたいとではその目的は完全に似て非なるものだった。
だからハンター試験が終われば、それ以上一緒にいるわけにはいかなかった。
「は、ハンターになったらどうするのだ?」
「え?」
「いや、無粋な質問だったな。すまない。……自由に、なったのだからな」
「……うん、そうだね、私は自由に……なりたかったから」
しかしそれは期限付きの自由でしかない。
本当の意味で自由になれないことは、自分自身が誰よりも理解していた。
それを知っていたからこそヒソカは、を檻の外から逃がしたのだ。飼い主が迎えに来ることを見越して。
――私は、死にたいと思ったんだよ。
そんなこと、この人の前では言えないなと、そう思っただった。
End

- Back Top
