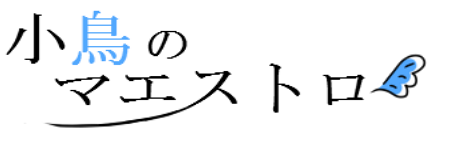

Episode.01 鎖にキス

目の前に並べられた宝飾品と目の前の男を交互に見つめる。一体何がしたいのだろうか。男、クロロは何も言わずにただ、不敵な笑みを浮かべているだけだった。
「土産だ」
「土産だなんて……盗んだものでしょう、要らないわ」
「そう言うな、興味が無いわけではないだろう」
確かに、どこぞから盗んできた宝石たちはどれもが競うように輝いて美しい。だがしかし、今し方伝えたようにこれらは全て盗みを働いて奪ってきたものなのだ。遠慮などでは決してなく、そんな汚れた美しさなど、本気で要らなかった。
男は拒絶の声など全く耳に入っていないようで、沢山の宝飾の中から大きな翠の石がついたペンダントを一つ取ると、女の首にかけて微笑んだ。
「ほら、とても良く似合っている」
「外に出られもしないのに、飾る必要なんてない」
されるがままの女は、それだけ呟くと眼を閉じる。美しいと、耳元で囁かく声が癪に障る。
「クロロ」
「どうした、。俺の為に歌う気になったか?」
「いいえ、少し黙ってほしいだけ。貴方が居ない間はとても平穏だったわ」
どれだけ突き放したように言葉を吐いても、クロロはただ楽しそうに笑うだけだった。怒らせて、いっそ殺されたいとが思ったところで、彼にその気は全く無いのである。
「不思議なものだな。どれだけ生に価値があろうが、今までそれを欲したことなど無かったと言うのに」
「貴方のお眼鏡にかなってしまった、私はとても不幸ね」
「そうだな。同情するよ」
泣きたいほどに、クロロは冷酷だった。それでもは淡々と返し、決して弱みは見せまいと気丈に振舞う。その様子こそが、彼の興味を惹いていることに気がつきもせずに。
しかし不思議と、自害しようとは思わなかった。別に他の仲間が旅団の誰かに殺されたわけでもない。いや、もしかしたら既に壊滅させられているかもしれないが、それを知る術など最早自分にはないのだ。とにかく、クロロが自分をコレクションとしてではあるが、大事にしているのが解っていたから、これまで逃げる素振りなど一度も見せたことはなかった。どうして、逃げようと思わなかったのだろう。恐らくは自身が、中途半端に念を覚えていたからに過ぎなかった。決して強いわけではない自分のオーラが、目の前の男には敵うはずも無いことを理解してしまっていた。戦う前から、諦めてしまっていたのだ。
「あれ以来、俺はお前の歌声を聞いたことがないんだが」
「……」
「マチやシャルナークの話によれば、俺が不在の間は何度か聞こえてきたらしい」
誰かの為に歌うなんて、御免だ。それも、こんな性悪な男の為になど誰がと、はただただ反発した。翼を失った一族である自分から、更にこの男は自由を奪った。重たい枷で繋ぎとめて、見下して嘲り笑うのだ。憎い相手の為に歌えと。
「貴方が死んだら、鎮魂歌 を歌ってあげる。私が先に死ぬときは、断末魔と言う名の、永遠の子守唄 を」
「……お前のことだ、断末魔も美しいだろうな」
「……!!」
少し、興味が沸いた。そう囁いたかと思えば、ペンダントの上から首を絞められる。徐々に徐々に、強くなっていく力。
「……ッ、は」
「どうした、歌わないのか」
まだ、殺す気などないくせに。声など出してやるものか。
酸素を失い蒼くなっていく女の顔と、それでも声を出そうとしない意志の強さに苛立ちを覚える。やがての首から手を離したクロロは、酸素を求めて大きく肩で息をする彼女を見下ろしながら
「……どうしたら、お前は」
小さく呟いて、止めた。これ以上本気で求めてしまえば、物欲以外の感情が芽生えてしまったら、絶対に手に入らないであろう彼女を殺してでも自分のものにしてしまいたくなるかも知れないからだ。
クロロの呟きは苦し気に息をするには聞こえない。聞こえていたら、この先何かが変わっていたのだろうか。
床に倒れこむを一瞥すると、クロロは無言のまま部屋を出た。
――どうしたら、お前は俺のモノになる?
最初から力ずくで奪ってしまったことで、身体は手に入ろうとも心は決して堕ちないことを理解している。だからこそ、余計に腹立たしく思うのだ。最近の団長は少しおかしい、と団員達に噂されているのも知っている。しかし、それ程までに魅了されてしまったのだ。あの日の彼女の歌声に。
幾月が経ったある日のこと。
暫く不在にしていた仮宿に戻ってきたクロロは、お気に入りのコレクションを繋いでいた鎖が切られているのに気がついた。
「……が逃げた?」
「ごめん、団長……」
「シズク、今回の見張りはお前か」
「うん、あとヒソカ」
そこまで聞くと、クロロは嘆息する。やはりというべきか、それはまあまあ想定内の出来事である。
そうなると、大体の居場所は見当がつく。団員の中でも少し抜けているところのあるシズクは、一度集中すると周りが見えなくなる。更に忘れっぽい。何故、普段なら自分についてきたがるヒソカがシズクと共に仮宿の警護に残ったのか、合点がいった。
「シャル、ヒソカの場所は」
「ああ、ダメだね。ハンター試験はもう始まってるや。もしかしたらも」
「……まあ、良いだろう」
もし彼女が死んでしまうなら、それはそれで諦めもつくだろう。しかしあの声が聞けないとなると、惜しくも思う。
「試験が終わってから、迎えに行くさ」
「ふうん。ま、その時は手伝うよ。落ちたら早めに会場から出てくるかもしれないしね」
探しに行くと言わないところが団長らしいな、とシャルナークは自前のノートパソコンを閉じながら思う。最近の頭はどこかおかしいと感じながら、それでも決して止めないのは、この人が狂っていくのを見ていたいという興味的な何かが確かにあったからだ。団長への想いが人一倍強いマチは、の存在を面白く思ってはいないようだったが。
「俺も興味あるからさ」
シャルナークの意味深な発言に、クロロはただ「そうか」とだけ返した。
決して手に入らないなら、いっそあの時に殺しておけば良かっただろうか。彼女が望んだとおり、氷漬けにして寝台に飾ってしまえば良かっただろうか。
「死ぬなよ……」
クロロはその場に千切り捨てられたペンダントの鎖に口付けながら、願うように口にした。
決して手に入らないと知っているからこそ、美しく、それでいて愛しく思うのだ。
「土産だ」
「土産だなんて……盗んだものでしょう、要らないわ」
「そう言うな、興味が無いわけではないだろう」
確かに、どこぞから盗んできた宝石たちはどれもが競うように輝いて美しい。だがしかし、今し方伝えたようにこれらは全て盗みを働いて奪ってきたものなのだ。遠慮などでは決してなく、そんな汚れた美しさなど、本気で要らなかった。
男は拒絶の声など全く耳に入っていないようで、沢山の宝飾の中から大きな翠の石がついたペンダントを一つ取ると、女の首にかけて微笑んだ。
「ほら、とても良く似合っている」
「外に出られもしないのに、飾る必要なんてない」
されるがままの女は、それだけ呟くと眼を閉じる。美しいと、耳元で囁かく声が癪に障る。
「クロロ」
「どうした、。俺の為に歌う気になったか?」
「いいえ、少し黙ってほしいだけ。貴方が居ない間はとても平穏だったわ」
どれだけ突き放したように言葉を吐いても、クロロはただ楽しそうに笑うだけだった。怒らせて、いっそ殺されたいとが思ったところで、彼にその気は全く無いのである。
「不思議なものだな。どれだけ生に価値があろうが、今までそれを欲したことなど無かったと言うのに」
「貴方のお眼鏡にかなってしまった、私はとても不幸ね」
「そうだな。同情するよ」
泣きたいほどに、クロロは冷酷だった。それでもは淡々と返し、決して弱みは見せまいと気丈に振舞う。その様子こそが、彼の興味を惹いていることに気がつきもせずに。
しかし不思議と、自害しようとは思わなかった。別に他の仲間が旅団の誰かに殺されたわけでもない。いや、もしかしたら既に壊滅させられているかもしれないが、それを知る術など最早自分にはないのだ。とにかく、クロロが自分をコレクションとしてではあるが、大事にしているのが解っていたから、これまで逃げる素振りなど一度も見せたことはなかった。どうして、逃げようと思わなかったのだろう。恐らくは自身が、中途半端に念を覚えていたからに過ぎなかった。決して強いわけではない自分のオーラが、目の前の男には敵うはずも無いことを理解してしまっていた。戦う前から、諦めてしまっていたのだ。
「あれ以来、俺はお前の歌声を聞いたことがないんだが」
「……」
「マチやシャルナークの話によれば、俺が不在の間は何度か聞こえてきたらしい」
誰かの為に歌うなんて、御免だ。それも、こんな性悪な男の為になど誰がと、はただただ反発した。翼を失った一族である自分から、更にこの男は自由を奪った。重たい枷で繋ぎとめて、見下して嘲り笑うのだ。憎い相手の為に歌えと。
「貴方が死んだら、
「……お前のことだ、断末魔も美しいだろうな」
「……!!」
少し、興味が沸いた。そう囁いたかと思えば、ペンダントの上から首を絞められる。徐々に徐々に、強くなっていく力。
「……ッ、は」
「どうした、歌わないのか」
まだ、殺す気などないくせに。声など出してやるものか。
酸素を失い蒼くなっていく女の顔と、それでも声を出そうとしない意志の強さに苛立ちを覚える。やがての首から手を離したクロロは、酸素を求めて大きく肩で息をする彼女を見下ろしながら
「……どうしたら、お前は」
小さく呟いて、止めた。これ以上本気で求めてしまえば、物欲以外の感情が芽生えてしまったら、絶対に手に入らないであろう彼女を殺してでも自分のものにしてしまいたくなるかも知れないからだ。
クロロの呟きは苦し気に息をするには聞こえない。聞こえていたら、この先何かが変わっていたのだろうか。
床に倒れこむを一瞥すると、クロロは無言のまま部屋を出た。
――どうしたら、お前は俺のモノになる?
最初から力ずくで奪ってしまったことで、身体は手に入ろうとも心は決して堕ちないことを理解している。だからこそ、余計に腹立たしく思うのだ。最近の団長は少しおかしい、と団員達に噂されているのも知っている。しかし、それ程までに魅了されてしまったのだ。あの日の彼女の歌声に。
幾月が経ったある日のこと。
暫く不在にしていた仮宿に戻ってきたクロロは、お気に入りのコレクションを繋いでいた鎖が切られているのに気がついた。
「……が逃げた?」
「ごめん、団長……」
「シズク、今回の見張りはお前か」
「うん、あとヒソカ」
そこまで聞くと、クロロは嘆息する。やはりというべきか、それはまあまあ想定内の出来事である。
そうなると、大体の居場所は見当がつく。団員の中でも少し抜けているところのあるシズクは、一度集中すると周りが見えなくなる。更に忘れっぽい。何故、普段なら自分についてきたがるヒソカがシズクと共に仮宿の警護に残ったのか、合点がいった。
「シャル、ヒソカの場所は」
「ああ、ダメだね。ハンター試験はもう始まってるや。もしかしたらも」
「……まあ、良いだろう」
もし彼女が死んでしまうなら、それはそれで諦めもつくだろう。しかしあの声が聞けないとなると、惜しくも思う。
「試験が終わってから、迎えに行くさ」
「ふうん。ま、その時は手伝うよ。落ちたら早めに会場から出てくるかもしれないしね」
探しに行くと言わないところが団長らしいな、とシャルナークは自前のノートパソコンを閉じながら思う。最近の頭はどこかおかしいと感じながら、それでも決して止めないのは、この人が狂っていくのを見ていたいという興味的な何かが確かにあったからだ。団長への想いが人一倍強いマチは、の存在を面白く思ってはいないようだったが。
「俺も興味あるからさ」
シャルナークの意味深な発言に、クロロはただ「そうか」とだけ返した。
決して手に入らないなら、いっそあの時に殺しておけば良かっただろうか。彼女が望んだとおり、氷漬けにして寝台に飾ってしまえば良かっただろうか。
「死ぬなよ……」
クロロはその場に千切り捨てられたペンダントの鎖に口付けながら、願うように口にした。
決して手に入らないと知っているからこそ、美しく、それでいて愛しく思うのだ。
End

- Top Next
