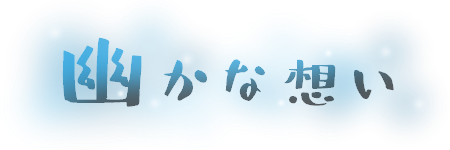

01

「まだ、あいつのこと引きずってんのか」
幼馴染で親友のエレンにそう言われたのは、訓練兵の卒業間近。エレンやミカサと共に自分も調査兵団を目指す、と打ち明けた頃だった。あいつとは誰のことを指しているのか、それはすぐにわかった。幸い周囲に人は居なかったので、誰かに聞き耳を立てられると言う心配も無かったことには安堵したが、それでもどうして今、こんな話をしなくてはならないのか。食堂で硬いパンをちぎりながら、アルミンはエレンのことを少し睨んだ。
「……引きずってるって、何? 忘れられるわけがないじゃないか」
エレンが母親のことを忘れられないように、アルミンだって彼女のことを忘れたりなんか決してしない。小さくて弱かったエレンが母親を助けられなかったように、弱くて臆病な自分は彼女を見捨てて、逃げたのだ。それなのに優しいあの時間を無かったことにして、のうのうと生きていくなんて許されるはずが無い。せめて、彼女が一緒に見てくれた夢を、実現させるために戦おうと決めたのだから。
訓練兵としての生活も残りわずか。相変わらずハードな訓練にボロボロでくたくたの毎日だ。それでも、生きているって実感する。自分は、生きている。彼女を見捨てて、逃げたおかげで。
「僕は、彼女のことだけは……捨てちゃいけなかったのに」
何かを変えるには、何かを捨てることの出来る人だと思う。その考えは変わっちゃいないけれど、それでも捨ててはいけないものは確かに存在する。自分の命より、大切だったはずなのに。
宿舎のベッドの上。四肢を投げ出して、天井――とはいっても二段ベッドの上段の底が見えるだけだったが――を見つめる。エレンには悪いと思ったが、さすがに食事を続ける気にはなれずサシャに残りのパンを譲ってアルミンは早々に部屋へと戻ってきた。
もうすぐ卒業。弱い自分が、ここまで来れたのだ。きっと、その先も生き抜いてみせる。途中で諦めて死んでしまったら、あの世で彼女に合わせる顔がないから。ああでも、天国へ行ったであろう彼女には、出会えないかもしれない。何せ、彼女を見殺しにしてしまった自分は恐らく地獄行きだろうから。
「……やめよう、もう」
忘れるわけにはいかないが、エレンの言うとおり、いつまでも引きずるわけにはいかないのだ。常に制服の胸ポケットに忍ばせているお守りに手を当てて、彼女の名を呼んでから眼を閉じた。
「」
もう、このまま眠ってしまおう。明日になればまたいつも通り、激しい訓練で彼女のことを思い出す暇もなくなってしまうだろうから。こんなに女々しいのは、今だけだ。
「……、」
しかし眠ろうと意識をすればするほど、目は冴えてしまって困惑する。だけど本当はわかっている。彼女との思い出が美しすぎて、訓練が苦しければ苦しいほど、記憶の中の彼女に縋ってしまいたくなる。
二度目に名前を呼んだ時、声が震えたのが自分でもわかった。ゆっくりと右手の甲を唇に当て身体を震わせる。こらえても、こらえようとしても、彼女のいない世界の全てに耐え切れず、じわりと涙が浮かぶ。仰向けに寝転がったベッドの上、目尻から細く一筋の雫が米神から耳の裏を通ってシーツを濡らした。
「本当に、好きだったんだ……君の事」
――うん、私も。
「……!?」
突如聞こえた声に、ベッドから跳ね起きる。聞こえるわけがない。大好きな彼女は、は、もうこの世にはいないのだ。これは幻聴だ。しかし、頭ではそう理解していても、大きく反応してしまう。ベッドから身体を起こしたアルミンは、部屋を見回して、落胆する。薄暗い部屋には、自分しかいない。わかっていたことじゃないか。彼女のことを見捨てたのは他でもない自分なんだから。
「はは……とうとう僕も、頭がおかしくなったのかな」
限界も近いのかもしれない、とマイナスなことばかりを自嘲気味に口にする。やがて、少しだけ開いていた窓の隙間から風が吹き込んできて、閉められたカーテンを揺らした。その間から月明りが差し込んできて、眩しさに咄嗟に窓を見て目を細めたアルミンは、
「……え?」
信じられないものを見た。
『私も、好きだよ。アルミン』
あの頃の、幼いままの少女が、そこには立っていた。。アルミンがその名を呼ぶと、少女は嬉しそうに目を細めて笑った。
『よかった、やっと気づいてくれたね』
ずっと待ってたんだよ、とが少しだけ唇を尖らせた。あの頃の彼女と何ら変わらない口調に、アルミンはやはりこれは自分が作り出した幻なのではと思う。けれども月明かりに照らされた彼女の身体が幻想的に透けていることと、ベッドに座っているとはいえアルミンよりも高い位置にある彼女の顔に、浮遊しているが、俗に言う霊魂なのだということを知る。
非現実だ。やはりこれは夢なのだ。彼女に会いたいがあまりに、自分は夢の中でを具現化しているに過ぎない。そう考えに及んだアルミンは、自然と自分の頬に手を伸ばした。人差し指と親指で頬を捻り上げ、じんわりとした痛みに顔を顰める。夢じゃない? では、目の前の彼女は。
「……本当に、君なの? ……」
『わたしはわたし、だよ。アルミン。お友達になってくれるって言ったのに、わたしのこと忘れちゃったの?』
「そ、そんなことない!」
忘れるわけがない。この数年間、夢に見なかった日はなかった。だって、あれは自分の初恋だったのだ。最悪な結末に、苦しくて仕方がなかった。
「でも、なんで……僕は君に、とても残酷なことをしたのに」
『……? 残酷って?』
本当にわからないといったように不思議そうな顔をするに、アルミンはぐっと唇を引き結んだ。瞳に涙を溜めながら、それでも懸命に言葉を紡ごうと必死だった。
「外の世界への夢を見せて、希望を持たせて、最後には君の事、裏切ったんだ……」
『……わたし、裏切られたなんて思ってない。あのときアルミンが来たって、ふたり一緒に死んでたよ』
だったら、アルミンだけでも生きていてくれて私は嬉しい。が心からそう言うので、アルミンは堪える間もなく涙を流した。ごめん、ごめんねと何度も謝りながら。
『わたし、ずっとアルミンの傍に居たのよ。だけどあなたはちっとも気づいてくれなくて』
「……どうして、僕の傍に?」
『だって、アルミンから離れたら真っ暗なの。だからわたし、どこへも行けない……』
せっかく自由の身になったのに壁を越えられなくて、アルミンの語った海も見に行けなかった。先に行って教えてあげようと思ったのに、と申し訳なさそうな顔をするに、アルミンは手を伸ばした。頭を撫でようとして、息を呑む。
伸ばした手が、の頭に触れることなく通過した。
「……っ」
『気にしないよ、アルミン。わたしは、今とてもうれしいの。苦しかった病気からも解放されて、アルミンともまたお話が出来る。とても素敵なことよ?』
「だけど、」
死んでいるのに、幸せなんておかしなことを言う。あの頃から成長をしていない目の前の存在を見ればわかる。に未来はないのだ。これから先、と自分がともに歩める未来なんて、ないのだ。いつ消えるとも知れない不安定な存在に、アルミンはたまらなく心が押し潰されそうになる。
『アルミン』
「……?」
『アルミンは優しいから、私を助けられなかったことで自分を責めているのね。……わたし、ずっと見ていたの。アルミンが眠っている間にうなされているときも、つらい訓練を頑張っているときも、わたし、傍にいたのに何もできなかった。だからわたしは、わたしがきらい』
「そんなことない! 、僕は――君が居たから、訓練兵になろうって思ったんだ」
『じゃあ、アルミンも自分ばかりを責めるのはもうやめて』
が泣きそうに顔を歪めるから、アルミンは苦しくなる。アルミンが自身を責め続けることで、が不幸になるなんて考えたことはなかった。後悔ばかりを繰り返したって、誰も幸せにはなれないのだ。
「……ごめん、」
『だから……!』
「うん。もう、これで最後にするよ」
『!』
もう、驚かない。通り抜けることを承知して、意味が無いとわかりながら、アルミンはの手に触れた。彼女の手を取ろうとしても、アルミンはただ自分の拳を握り締めただけだった。しかし、そんなことは些細な問題だ。気持ちの問題だ、と自分に言い聞かせ、アルミンは真っ直ぐにを見た。
「僕は、調査兵団に入るよ。絶対に夢を諦めたりしない。だから、」
それはどんな言葉よりも甘く、痺れるような
「僕と一緒に、外の世界を見に行こう」
愛の告白だった。
幼馴染で親友のエレンにそう言われたのは、訓練兵の卒業間近。エレンやミカサと共に自分も調査兵団を目指す、と打ち明けた頃だった。あいつとは誰のことを指しているのか、それはすぐにわかった。幸い周囲に人は居なかったので、誰かに聞き耳を立てられると言う心配も無かったことには安堵したが、それでもどうして今、こんな話をしなくてはならないのか。食堂で硬いパンをちぎりながら、アルミンはエレンのことを少し睨んだ。
「……引きずってるって、何? 忘れられるわけがないじゃないか」
エレンが母親のことを忘れられないように、アルミンだって彼女のことを忘れたりなんか決してしない。小さくて弱かったエレンが母親を助けられなかったように、弱くて臆病な自分は彼女を見捨てて、逃げたのだ。それなのに優しいあの時間を無かったことにして、のうのうと生きていくなんて許されるはずが無い。せめて、彼女が一緒に見てくれた夢を、実現させるために戦おうと決めたのだから。
訓練兵としての生活も残りわずか。相変わらずハードな訓練にボロボロでくたくたの毎日だ。それでも、生きているって実感する。自分は、生きている。彼女を見捨てて、逃げたおかげで。
「僕は、彼女のことだけは……捨てちゃいけなかったのに」
何かを変えるには、何かを捨てることの出来る人だと思う。その考えは変わっちゃいないけれど、それでも捨ててはいけないものは確かに存在する。自分の命より、大切だったはずなのに。
宿舎のベッドの上。四肢を投げ出して、天井――とはいっても二段ベッドの上段の底が見えるだけだったが――を見つめる。エレンには悪いと思ったが、さすがに食事を続ける気にはなれずサシャに残りのパンを譲ってアルミンは早々に部屋へと戻ってきた。
もうすぐ卒業。弱い自分が、ここまで来れたのだ。きっと、その先も生き抜いてみせる。途中で諦めて死んでしまったら、あの世で彼女に合わせる顔がないから。ああでも、天国へ行ったであろう彼女には、出会えないかもしれない。何せ、彼女を見殺しにしてしまった自分は恐らく地獄行きだろうから。
「……やめよう、もう」
忘れるわけにはいかないが、エレンの言うとおり、いつまでも引きずるわけにはいかないのだ。常に制服の胸ポケットに忍ばせているお守りに手を当てて、彼女の名を呼んでから眼を閉じた。
「」
もう、このまま眠ってしまおう。明日になればまたいつも通り、激しい訓練で彼女のことを思い出す暇もなくなってしまうだろうから。こんなに女々しいのは、今だけだ。
「……、」
しかし眠ろうと意識をすればするほど、目は冴えてしまって困惑する。だけど本当はわかっている。彼女との思い出が美しすぎて、訓練が苦しければ苦しいほど、記憶の中の彼女に縋ってしまいたくなる。
二度目に名前を呼んだ時、声が震えたのが自分でもわかった。ゆっくりと右手の甲を唇に当て身体を震わせる。こらえても、こらえようとしても、彼女のいない世界の全てに耐え切れず、じわりと涙が浮かぶ。仰向けに寝転がったベッドの上、目尻から細く一筋の雫が米神から耳の裏を通ってシーツを濡らした。
「本当に、好きだったんだ……君の事」
――うん、私も。
「……!?」
突如聞こえた声に、ベッドから跳ね起きる。聞こえるわけがない。大好きな彼女は、は、もうこの世にはいないのだ。これは幻聴だ。しかし、頭ではそう理解していても、大きく反応してしまう。ベッドから身体を起こしたアルミンは、部屋を見回して、落胆する。薄暗い部屋には、自分しかいない。わかっていたことじゃないか。彼女のことを見捨てたのは他でもない自分なんだから。
「はは……とうとう僕も、頭がおかしくなったのかな」
限界も近いのかもしれない、とマイナスなことばかりを自嘲気味に口にする。やがて、少しだけ開いていた窓の隙間から風が吹き込んできて、閉められたカーテンを揺らした。その間から月明りが差し込んできて、眩しさに咄嗟に窓を見て目を細めたアルミンは、
「……え?」
信じられないものを見た。
『私も、好きだよ。アルミン』
あの頃の、幼いままの少女が、そこには立っていた。。アルミンがその名を呼ぶと、少女は嬉しそうに目を細めて笑った。
『よかった、やっと気づいてくれたね』
ずっと待ってたんだよ、とが少しだけ唇を尖らせた。あの頃の彼女と何ら変わらない口調に、アルミンはやはりこれは自分が作り出した幻なのではと思う。けれども月明かりに照らされた彼女の身体が幻想的に透けていることと、ベッドに座っているとはいえアルミンよりも高い位置にある彼女の顔に、浮遊しているが、俗に言う霊魂なのだということを知る。
非現実だ。やはりこれは夢なのだ。彼女に会いたいがあまりに、自分は夢の中でを具現化しているに過ぎない。そう考えに及んだアルミンは、自然と自分の頬に手を伸ばした。人差し指と親指で頬を捻り上げ、じんわりとした痛みに顔を顰める。夢じゃない? では、目の前の彼女は。
「……本当に、君なの? ……」
『わたしはわたし、だよ。アルミン。お友達になってくれるって言ったのに、わたしのこと忘れちゃったの?』
「そ、そんなことない!」
忘れるわけがない。この数年間、夢に見なかった日はなかった。だって、あれは自分の初恋だったのだ。最悪な結末に、苦しくて仕方がなかった。
「でも、なんで……僕は君に、とても残酷なことをしたのに」
『……? 残酷って?』
本当にわからないといったように不思議そうな顔をするに、アルミンはぐっと唇を引き結んだ。瞳に涙を溜めながら、それでも懸命に言葉を紡ごうと必死だった。
「外の世界への夢を見せて、希望を持たせて、最後には君の事、裏切ったんだ……」
『……わたし、裏切られたなんて思ってない。あのときアルミンが来たって、ふたり一緒に死んでたよ』
だったら、アルミンだけでも生きていてくれて私は嬉しい。が心からそう言うので、アルミンは堪える間もなく涙を流した。ごめん、ごめんねと何度も謝りながら。
『わたし、ずっとアルミンの傍に居たのよ。だけどあなたはちっとも気づいてくれなくて』
「……どうして、僕の傍に?」
『だって、アルミンから離れたら真っ暗なの。だからわたし、どこへも行けない……』
せっかく自由の身になったのに壁を越えられなくて、アルミンの語った海も見に行けなかった。先に行って教えてあげようと思ったのに、と申し訳なさそうな顔をするに、アルミンは手を伸ばした。頭を撫でようとして、息を呑む。
伸ばした手が、の頭に触れることなく通過した。
「……っ」
『気にしないよ、アルミン。わたしは、今とてもうれしいの。苦しかった病気からも解放されて、アルミンともまたお話が出来る。とても素敵なことよ?』
「だけど、」
死んでいるのに、幸せなんておかしなことを言う。あの頃から成長をしていない目の前の存在を見ればわかる。に未来はないのだ。これから先、と自分がともに歩める未来なんて、ないのだ。いつ消えるとも知れない不安定な存在に、アルミンはたまらなく心が押し潰されそうになる。
『アルミン』
「……?」
『アルミンは優しいから、私を助けられなかったことで自分を責めているのね。……わたし、ずっと見ていたの。アルミンが眠っている間にうなされているときも、つらい訓練を頑張っているときも、わたし、傍にいたのに何もできなかった。だからわたしは、わたしがきらい』
「そんなことない! 、僕は――君が居たから、訓練兵になろうって思ったんだ」
『じゃあ、アルミンも自分ばかりを責めるのはもうやめて』
が泣きそうに顔を歪めるから、アルミンは苦しくなる。アルミンが自身を責め続けることで、が不幸になるなんて考えたことはなかった。後悔ばかりを繰り返したって、誰も幸せにはなれないのだ。
「……ごめん、」
『だから……!』
「うん。もう、これで最後にするよ」
『!』
もう、驚かない。通り抜けることを承知して、意味が無いとわかりながら、アルミンはの手に触れた。彼女の手を取ろうとしても、アルミンはただ自分の拳を握り締めただけだった。しかし、そんなことは些細な問題だ。気持ちの問題だ、と自分に言い聞かせ、アルミンは真っ直ぐにを見た。
「僕は、調査兵団に入るよ。絶対に夢を諦めたりしない。だから、」
それはどんな言葉よりも甘く、痺れるような
「僕と一緒に、外の世界を見に行こう」
愛の告白だった。
to be continued...

- Back Top
